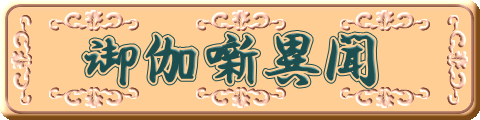
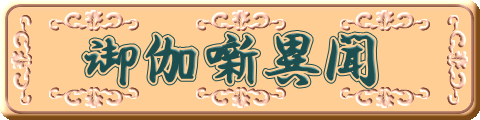
そもそもの発端は、宮廷お抱えの理髪師が続けて二人、謎の死を遂げたことだ。
表向きは病死という話だったが、ある日を境に宮廷から帰って来なかったというのが本当の話らしい。
失踪の理由はもちろん不明ってやつだ。残された家族は王宮に訴えに行ったらしいが、そのまま追い返されて話はそれで終わり。
街での嫌な噂話ってやつだな。
だが俺は、そんなこととは露とも知らなかった。知っていたならば、宮廷からの誘いなんか受けなかっただろう。床屋ってところは街の噂話が集まるはずなんだが、お客が一人も来ない床屋には噂話も寄って来ない。
困ったもんだね。
客が来なくなった理由は薄々わかっている。一年ほど前に、ヒゲが自慢のお客さんのそれを、寝ている間に綺麗に剃り落としたからだと思う。
だって嫌な奴なんだぜ。そいつは。
嫌味のお返しに綺麗にヒゲ剃りをしてやったんだから、お礼こそ言われても嫌がらせをされる道理は無い。だけどまあ、そいつは街の顔役って奴で、それで俺の店には閑古鳥が鳴く羽目になっちまった。
知ってるかい?
閑古鳥の鳴き声ってのは静かなものなんだぜ。あまりに静かで堪らないので、俺は店で一人でお喋りを続けた。俺は元来一人が嫌いなタチで、だからいつも人が集まるようにと床屋を始めたんだ。それなのにこの有様。俺はちょっとばかしおかしくなっていた。
そこにやって来たのが、宮廷からの使者ってやつだ。
そなたの腕を見こんで王様の髭を剃って欲しい。宮廷お付きの理髪師として採用したい。
流行らない店の主人が、ピカピカのお仕着せを着た侍従たちにそう告げられたならば、躍り上がって喜ぶのが普通だろう?
俺は疑わなかった。
周囲を兵士に固められてお城に案内されたときも、それが普通のことだと思っていた。
今まで見たことが無いような大きなピカピカの広間に通されて、いかにも時代を思わせるテーブルの上に、銅張りの年代物の鏡が置かれているのを見たときには、その豪華さに正直震えが来たね。湯気を立てるお湯が一杯に入った金の盥の横には、頭がじんと痺れるような香りの高級な香料の入ったビンがずらりと並ぶ。石鹸もそうだ。王族が使う石鹸というものが存在するなら、まさにあれがそうだ。まるで磨きこまれた宝石のような色合いの石鹸なんて想像できるかな。
まあ、そのテーブルの前に座っていたのは豪華な衣装を着た初老の男だった。太っていたが、同時にどことなくやつれて見える。
でも、ごく普通の男だったよ。王様は。
普通じゃなかったのは髪がひどく乱れていて、頭に耳が隠れるほどの大きな毛糸の帽子を被っていたこと。その上に王冠を載せていたから似合わないことこの上ない。
王様が口を開いた。
「そちが余の新しい理髪師か」
いつの間にか案内役は消えていて、俺は一人だった。
「苦しゅうない。近くに寄れ。余は長きに渡りこの汚き頭のまま過ごしている。ただちにそちの働きを見せよ」
閉まった扉の向こうでガシャガシャと金属が触れ合う音がした。鎧を着た兵士たちが大勢待ち構えているのが感じ取れた。
そこまで来て初めて俺は思い当った。たしかこの王様、兄とその家族を皆殺しにして王位についたはず。それまでは悪名高い地方領主で、臣民を遊び半分で串刺しにして喜んでいたという噂を持っていた。
目の前にいるこの初老の男こそは王様という名前のついた絶対権力者。
俺は王様の前に跪いた。
「さっそく始めてもらいたい。だがその前にそちは余に一つ約束しなくてはならない」
王様の目が厳しくなった。
「何なりと」俺の口から言葉が返る。どこで覚えたんだ、こんな口調。
「これから目にするものは決して他言は無用。他言しようとしただけでも命を落とすことになる」
ああ、俺がこのとき、ここに来た他の連中の運命を知っていたらなあ。
俺の返事を待たずに、王様は自分の頭から王冠と毛糸の帽子を剥ぎ取った。
いや、それを見たときの俺ときたら。一瞬、自分の目を疑ったものだ。
王様の耳はロバの耳だ。王様の耳はロバの耳。
作り物かとも考えた。これは王様の性質の悪い冗談で、ロバの耳を見て笑った人間の首をちょん切るという遊びなのだと。
でも俺は笑わなかった。それはどう見ても本物の耳で、しかも正真正銘ロバの耳だったから。産毛まできちんと生えたロバの耳。王様の神経質な気分を反映するかのように小刻みに動いている。耳の表面の血管までもが透けて見えた。
深刻なトラブルに自分が嵌りこんだことを示す、下腹にずしんと来るあの嫌な感じ。
王様が何をやってロバの耳を頭につける羽目になったのか、俺は知らない。だが俺はそれを見てしまったのだし、王様もその側近も俺がそれを見たことを知っている。
最大級のトラブルだ。
俺は必ずこれを誰かに喋ってしまう。ゴシップ話の大好きなこの俺が、これだけの話を他人に喋らずにはいられるものか。例え自分の命がそれに掛かっているとしても。
それが自分でもわかっているから、俺の命は風前の灯だ。
震える指で苦労しながらも、俺は王様の髪を整え、ロバの耳の無駄毛を剃り落とした。
三日間だけはもったと言っておこう。俺にしては大したもんだと褒めてやりたい。
だけど限界が来た。俺の頭の中はロバの耳だけで一杯になった。
誰かに話したい。王様の耳がロバの耳だってことを。
道ですれ違う人にも話したいし、街の店という店の中で話したい。できれば王宮の前で大声で叫びたい。
王様の耳のことを。
きっと俺の話を聞いた人は目を丸くして驚くぞ。嘘つき呼ばわりもされるかもしれない。でも最後には目を輝かせて、俺の話に聞き入るだろう。ああ、その光景を想像しただけで体が震える。
だけど言えない。言えば殺される。
俺はもう失踪した二人の床屋の話を聞いてしまったのだから。きっと彼らの死体はときたま街の噂に上る王宮の地下牢の中だろう。
最近では王宮に王様の髪を整えに行っていないときは、俺の店にもちらほらと客が来るようになってきた。どれも見慣れぬ顔の目つきの鋭い客たちだ。
見張られている。そう感じた。
彼らは王様の耳のことは知らないが、俺が王様について怪しげな事を言い出したら、即座に殺せと命じられているのかもしれない。
考え過ぎだって?
俺はそうは思わない。
時おり、宮廷お付きの床屋になった俺のところに、近所の連中が顔を出すことがある。何か王宮について面白い話が無いか聞くためだ。だがそんなときには決まって、目つきの鋭い男が近くにいて、聞き耳を立てている。
喋りたい。
喋りたい。
喋りたい。
大声でみんなに喋りたい。王様の耳がロバの耳であることを。
王様には俺の心がじりじりと限界に達しかけているのがわかったのではないだろうか。
ある日、手に大きな斧を抱えて一人の兵士がやって来た。兵士は頭に包帯を巻いていた。そして俺の顔を見ると、兵士は大きな声で話し始めた。
「貴様が王様の話していた床屋だな。最初に言っておくが俺はお前の見張り番であり、おまけに処刑人でもある。貴様が誰かに何かを話しているところを見たら、躊躇わずに殺せと言われているし、実際にそうするつもりだ。それと俺に話しかけるのも無しだ。そうしても殺す。そもそも俺は何も聞けないようにこうして耳を潰されている」
兵士は自分の頭に巻かれた包帯を指さした。
「俺はこの仕事を最後まできっちりとやり遂げるつもりだ。お前が抱えている秘密が何かは知らんが、それが漏れた場合は俺の妻と娘が死ぬことになっている」
兵士はそれ以来、二度と俺には話しかけようとはしなかった。ただ店の片隅に座り、俺をじっと睨んでいるだけとなった。
俺は独り言さえも喋ることができず、ストレスが最高潮に達した。
このままでは発狂する。そう感じるようになったとき、解決策を思いついた。
俺はいつも、店の二階に寝泊りしているが、実は奥の壁には大きな穴が開いていて、そこから隣の屋根を伝ってこっそりと外に出ることができる。ずいぶん前に古くなった壁が崩れたときから何とか修理をしようとしていたのだが、金が無くて修理を延ばし延ばしにしていた。それが逆に役に立ったわけだ。
夜になるのを待って、俺は自分の店から忍び出た。
そのまま街はずれにある古い空き地に向かう。目的は空き地の寂れた住居跡にある古井戸だ。
周囲に誰もいないことを確認すると、俺は井戸に顔を突っ込み、叫んだ。
王様の耳はロバの耳だ。王様の耳はロバの耳。
胸がすっとした。
次の日も、その次の日も、俺は井戸へと忍び、同じセリフを叫んだ。
だが、そんな日々も長くは続かなかった。
ある夜、井戸に行くと、その中から声が聞こえて来たからだ。
『おうさまのみみは~』
ひいい。おれの喉から変な音が出た。
これはもう明らかな怪奇現象だ。誰もいない井戸の中から歌が聞こえる。いや、それよりも何よりも、このままでは誰かが王様の秘密を知ってしまう。歌の元が、俺の喉であろうが、井戸であろうが、どっちにしろ犯人は俺ということになる。
処刑人の斧が見えた気がした。
俺は慌てて家に戻ると、シャベルを持って来て、朝までかかって井戸を埋めた。
そんな事もあって、しばらくは俺も大人しくしていた。だが、その平穏も長くは続かず、またぞろ俺は誰かに王様のロバの耳のことを聞かせたくなった。
もちろん、人に聞かせるわけにはいかない。井戸もダメだ。
今度は西の野原に出かけることにした。街の西には誰も住まない葦の野原が広がっている。深夜にそこに赴き大きな声で叫んだ。
「おうさまのみみは~」
胸がすっとした。他の人間に聞かせるほどの爽快感はないが、それでも欲求不満のはけ口にはなる。
だが、そんな日々も長くは続かなかった。
ある夜、野原に行くと、風に揺れる葦の原から声が聞こえて来たからだ。
『おうさまのみみは~』
「ロバの耳だ~」思わず答えてしまってから、俺は蒼くなった。
これはまずい。流石にまずい。今はまだ深夜だから、この寂れた場所には人っ子一人もいないが、朝になれば旅人も通る。明日という日が終わる頃には、王様の耳のことは街中の噂になっているだろう。
ここに至ってようやく俺は理解した。王様の耳がロバの耳になったのは、きっとどこかの偉い神様を王様が怒らせたからだ。そうでなければ、これほどの怪奇現象が立て続けに起こるわけがない。
しかし、如何にこれが王様の日ごろの行いが悪かったせいだとしても、その責任を取らされるのは他でもないこの俺だ。
処刑人が血塗れの斧を持つ姿が頭に浮かんだ。
これはまずい。大変にまずい。大ピンチだ。
もう後先を考えている時間は無い。俺は葦の原に火をつけた。
威勢良く燃え上がった炎は、おりから吹き始めた強風に乗って、たちまちにして葦の原全体に広がった。誰かに目撃されない内にと俺は慌てて家に戻った。
翌日にはもう街中が葦の野原の大火事で持ち切りだった。火は街へも移りかけ、大変な騒ぎの末にようやく延焼を食い止めることができたらしい。
幸い、誰も王様の耳のことを噂する者はおらず、俺はほっと胸を撫で下ろした。
だが、これで終わりだなどとは俺は思っていなかった。
一週間も経たないうちに例の衝動が戻ってきた。
叫びたい。王様の耳のことを誰かに。王様の耳は実はロバの耳なんだ。そう街中で叫んで回りたい。
その衝動が抑えきれなくなって、俺はまた深夜に家を抜け出した。
今度は街の中心を流れる川を選んだ。街中の汚物が流れ込むのでこの川の下流は汚れているが、上流側はまだ綺麗に澄んだ水が流れている。
俺は暗闇の中、その川の流れに頭を沈めて、水中で大きく叫んだ。
「おうさまのみみは~」ゴボガバゴボガバ。「ロバの~耳だ~」ブクブクバゴバゴ。
危うく溺れ死ぬところだったが、胸はすっとした。話を聞いてくれる相手が川であって人間ではないのがちと残念だったが、この際だ、贅沢は言ってられない。
一週間は平穏な日が続いた。だが、一週間と一日目に、俺は街でどえらい話を聞いてしまった。
街の中を通り抜ける川で奇妙な歌声が聞こえるとか。
走った。俺は走った。川目指して。
川にかかる橋の上は物見高い見物客で一杯で、そいつらが皆、耳を澄まして川から流れて来る歌声を聴いていた。
『おうさまのみみは~』川が歌うと、見物客も一斉に唱和した。『ロバの~耳だ~』
ひい。思わず声が出た。もう駄目だ、という絶望が俺の体を突き抜けた。
今から川の水を全部飲み干したとしても、街中の人々がこれを聞いてしまったのでは、もう手遅れだ。
いや、まだ間に合う。俺は思い直すと自分の家へと走った。店にはあの兵士はいなかった。すべてを悟って、俺を殺す代わりに、まず自分と自分の家族を守りに走ったのだろう。賢い奴だ。
俺は店の正面から飛び込み、部屋の中の目ぼしいものを掻っ攫うと、反対側のドアから飛び出した。
危機一髪。
俺が家から飛び出したのと、王様の処刑人たちが俺の家へ飛び込むのはほぼ同時だった。
王様の追手は執拗だったが、こちらも命がかかっている。俺は逃げて逃げて逃げ続けた。
一つの街から次の街へ、追手がかかる前に、また次の街へ。
そのうち、俺はあることに気がついた。どのみち、王様の手のものに捕まれば死刑が待っているのだ。となれば・・・もう我慢する必要はない。
喋って喋って喋り倒そう。王様の、とっても素敵な、ロバの耳のことを。
どうせやるならと俺はド派手な格好をすることにした。色違いの布をツギハギに仕上げ、頭には羽飾りのついた大きな帽子を載せ、顔にはこれ以上無いってくらいの化粧を施した。ついでに大きなロバの耳の作り物もつけた。
街の広場に突然現れ、笛を吹き鳴らして人々の注意を集めると、俺は歌い始めた。
「王様~の~耳は~ロバの~耳だ~」
たちまち周囲は拍手喝采。最後は皆で王様の耳を歌った。
血相を変えた兵士たちが現れるとみるや、あらかじめ下調べをしてあった道を全力で走って逃げ、次の街へと進んだ。
楽しい。うれしい。そして面白い。
権力者が必死で隠す秘密をまき散らすのがこれほどまでに楽しいとは。
やがて俺の事は有名になり、ついでに誰もが王様の耳のことを話題にし始めた。俺が新しい街に現れると町中から人が集まり、俺の姿を一目見ようとするようになった。俺が楽器を掻き鳴らし、ロバの耳を歌うと、拍手と唱和が巻き起こった。
誰もが王様の耳を話題にし、まるでお天気について話すかのように、日常の挨拶にした。
笑いながら。
やあ今日のロバの耳はどうですかな。いや良いロバ耳日和で。おっといけない王様に聞かれたら大変だ。なにせあのロバの耳はよく聞こえるそうですからなあ。
王様の最大の失敗は、それに過剰に反応したことだ。
ちょうど王国の領土をほぼ一周したとき、最初の街で人死にが出た。
王様の耳の歌を口ずさんでいた少年が、兵士に捕らえられた挙句に死刑になったのだ。
殺気立った街の人々が広場に集まったそのときに、ちょうど俺が居合わせた。いまやすっかりと身に馴染んだ衣装に包まれて、俺は笛を吹き鳴らして歌った。
「王様の耳は~」それに答えた人々の口調には怒りがこもっていた。「ロバの耳!」
兵士たちが飛んで来た。俺はその捕縛の腕から逃れながら、それでも歌い続けた。
拳が上がり、棒が振り回され、剣が抜かれると、怒号が上がった。
俺は手にした笛で兵士の頭の横を殴ると、その場を後にした。
次の街ではもっとひどかった。
まず兵隊たちの顔つきが違う。必死の形相だ。あの王様の事だ、きっと俺を捕まえるのに失敗したら自分たちが代わりに処刑されるとでも言い渡されているのだろう。
俺も必死だ。ここまで来たらもう元には戻れない。全力で歌い、全力で逃げ、ついでに少しだけ戦った。
俺の周りに集まっていた街の連中もとばっちりを受けた。何人かはこの衝突で死んだかもしれない。
それでも俺は歌うのを止めなかった。
今更これを止めて何になる?
そんなことを続けているうちに、俺には新しい仲間が一人できた。一緒に王様のロバの耳について歌い、一緒に戦い、一緒に逃げる仲間だ。王様の命令で殺された最初の少年の父親だとは後で知った。
俺を追いかける兵士の数は膨れ上がり、それに呼応するかのように仲間も増えていった。
あの耳を潰された兵士も加わった。俺の街で床屋をやっていた他の連中も。帽子屋の組合やロバを飼うことを禁止された牧畜業者も戦いに加わった。
たまには王様の兵隊の方を負かし、街の広場で堂々と歌い続けることもあった。今では誰もが王様のロバの耳について知っていた。
王様の軍隊が、執拗に歌を歌い続ける街を一つ丸ごと焼き払った頃には、ロバの耳歌唱隊は大軍団に膨れ上がっていた。
時勢に敏感な教会は王様を悪魔崇拝の罪で破門し、あちらこちらで徴税官が袋叩きにあった。給与が滞ったことにより王側の兵士たちに逃亡が相次いだ。
今日、俺たちは反乱軍を率いて、王様の城を目指す。
明日には俺たちは王様の城を包囲しているだろう。
王様の体からロバの耳がついた頭を刈り取る日もそう遠くはない。