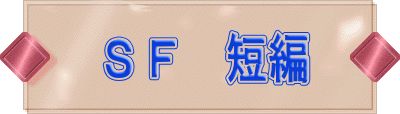
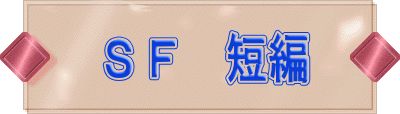
1)遺跡
その日の遺跡探検には予感があった。
遺跡探検とは一言で言えば木の根が蔓延った洞窟をさ迷うことだ。
この洞窟は元は大きな地下軍事基地であった。それがほぼ五百年前のことになる。文明崩壊とともに基地は最初は忘れ去られ、そして二百年前の遺跡発掘ブームで再度注目された。大勢の発掘屋がここを訪れ、様々な古い遺物を手に入れて金持ちになり、最後にはすべてを掘り尽くした。
十の歳からかれこれ二十年間、俺はたまにここを訪れてごく稀に見つかる遺物を探した。当然残された遺物は減っていき、最後はただ何もない洞窟をさ迷うだけとなった。最初は皆が無視していたスクラップでさえも、最後は目の色を変えて漁ることになった。
その間も俺の村は段々と寂れて行った。
それは俺の村だけではなく、各地に点在する人間の集落も同じだった。新しい文明の再興もできず、旧文明の遺跡を漁るだけの人類に未来は無かった。
もう何度も漁った洞窟を、それでも先人が見逃した何かがないかと往復する。俺が歩いているのは元は基地の主廊下であり、基地全体をつなぐ巡回路のハブの中心だ。地上から伸びて来た木の根が破れた天井から侵入し、辺りを埋め尽くしている。基地自体はスーパーコンクリートで作られているが、木の根は酸を出してそれを容赦なく浸食していく。
俺は松明を手にそこを歩いていた。
分岐点を五つ数えた所で、俺はふと思ったんだ。どうしてこの五つ目の分岐点だけ、前の分岐点との間隔が長いのだろうかと。
どこからその考えが出たのかは分からないが、一度そう思い始めるともう駄目だった。その考えは俺に取り憑いたんだ。
どうせそれ以上探しても掘り尽くされた遺跡にお宝なんかありゃしない。だから最近では俺以外の発掘屋は誰もここには潜らない。時間の無駄だからだ。
紐を持って戻り、分岐点の間隔を正確に測る。どうみても、四番目の分岐点と五番目の分岐点との間に、もう一つ分岐点が無ければおかしい。
この辺りと当たりをつけた場所を慎重にまさぐって見た。壁を這う木の根を叩き切り、積もった土砂を掘り進む。目を瞑ってから、歳月に浸食された壁に手を這わせてみる。一部感触が違う。ここだけスーパーコンクリートではなく、微かに冷たく感じる金属でできている。
細い筋を見つけたときには跳びあがらんばかりに興奮した。隠し扉だ。なるほど暗い洞窟の中でこれは見つからない。敏感な指先で触って初めて分かるものだ。
もちろん扉は開かない。手がかりもないので強引に開けることもできない。
だが俺は経験を積んだ発掘屋だ。扉の右側を探りもう一つの小さな隠しパネルを見つけた。これもうまく偽装していて、ぱっと見には分からない。
パネルを強く押す。遺跡が生きていた場合はこれで操作パネルが発光する。こいつは死んでいるので何も起きない。
俺は装備の中から虎の子のネオ・テルミット爆薬を取り出した。もの凄く高いのでおいそれとは使えない代物だ。これは前文明の遺物ではなく、火薬村と呼ばれているところで作られているものだ。俺たちの今の文明レベルではこれを作るぐらいがせいぜいだ。
これは単純な爆弾ではなく指向性を持たせたものだ。発火するとジェット噴流が主軸に沿って噴出するようになっている。
操作パネルの上に爆薬を張り付け、十分に離れてから起爆する。
静かなしゅっと言う音がして、続いてパンと弾ける音がした。
今の一瞬で二か月分の食料が買える金額が煙になった。これで扉が開かなかったら俺は泣くぞ。
操作パネルがあった場所には煙を上げる穴が開いていた。その中に細い鉤棒を突っ込み、中から配線を引き出す。
どんなに複雑な電子暗号鍵も、結局最後は扉を動かす電動モータへの給電ケーブルへと収束する。つまり鍵の最後の段階ではこの給電ケーブルに電流を流して扉を開くのだ。
引き出した配線の中で一番太いものを二本引き出す。赤と黒は何千年も前から変わらずに使われているケーブルの色だ。俺は携帯バッテリを配線につないだ。
それから一気に電流をかけた。
小型モータには暗号を入れないと動かないものが多いが、どういうわけか大型モータにはそんなものはついていない。隠し扉が一瞬震えると、恐ろしくゆっくりと開き始めた。動きにつれてきしみ音がする。この扉が遺跡と同じ古さなら、五百歳なのだから当然と言えば当然だ。
ちらりと扉の内側が見えた。壁は赤と黄色のダンダラ模様。
死の予感に背筋が凍りついた。
息を止め、震える手で装備の中から簡易酸素マスクを取り出して顔に嵌める。
開いた扉の隙間から風が吹き出した。それは止まることなく吹き出し続ける。
手首のチェッカーを覗く。表示は窒素濃度99%。やはりだ。この風を一口でも吸い込んだら、昏倒してそのまま窒息する。
赤と黄色のダンダラ模様は窒素充填区画を示す。部屋の中に窒素を充填して封鎖してあるということだ。酸素が無ければ内部の装備の劣化は最低限度まで抑えられるし、生物の侵入も防げる。ということはこの分岐点の先にあるのは極めて厳重に保存され、そして今まで誰も発掘していないお宝ということになる。
俺は内心で小躍りした。発掘屋なら誰でも、死ぬ前に一度は出会いたいと夢見る状況だ。
俺はもう一度簡易酸素マスクを確かめると、部屋の中に足を踏み入れた。
外とは違って、この通路には木の根も塵もない。まるで昨日作られたばかりのようにどこもかしこもピカピカだ。俺が足を踏み入れると、弱弱しいが壁面発光が始まった。驚いたことにここの電子回路は五百年の歳月を越えてまだ生きている。
通路の先には巨大な倉庫が三つ待ち構えていた。各種の器材を詰めた箱が天井までぎっちりと詰まっている。樹脂に封入された電子素材、金属部品、各種素材に、高磁場停止装置内に保存された薬品類。まさに宝の山だ。なるほどここの持ち主が厳重に封印して隠しただけはある。
これはもしかしたら帝都すら丸ごと買える規模のお宝じゃないか。そう思うと今になって興奮に足が震えてきた。
ここの壁に設えられているパネルを操作すると備蓄部品のリストが出た。表示は前文明文字だ。発掘屋なら誰でもこれを読めるのが普通だ。
そこに並ぶ内容に俺は目を剥いた。どれ一つ取っても一財産だ。これほどのジャックポットは二百四十年前のザンドール峡谷遺跡の備蓄所発見以来であることは間違いない。あのときは帝国中が大騒ぎになったと聞いている。
光量子コンピュータのクリスタルコアに帝都アカデミーの連中がいったい幾らの懸賞金を懸けていると思う? それはもう凄いものだ。
取り合えず目ぼしい物を適当に選んで折り畳みリュックに詰め込んだ。これだけでも俺は大金持ちになれるだろう。
帰ろうとして荷物を背負いあげると、首筋がちくりとした。反射的に手で叩くと手の平の中で一匹の蚊が潰れていた。
悪態をつきながら歩みを進めようとして、その場に凍り付いた。背中を嫌な冷たいものが滑り落ちる。
チェッカーの表示を再度見る。窒素濃度98%。扉を開けたことで封入窒素と外気が混ざりさっきよりはやや濃度が落ちている。それでも差し引き酸素濃度はわずかに2%。
これは簡易酸素マスクを取れば、その場で昏倒して死ぬ濃度。間違っても蚊が生きていける酸素濃度ではない。
バッグから取り出した袋の中に手のひらの蚊の残骸を入れる。
それから絶望の気分を抱えたまま俺は村への帰路についた。
2)盗掘村
村に着いたときはすでに夕刻だった。夕日は地平線にかかり、今日に限ってやけに血のように赤い空を演出している。
村は木造りの柵で囲まれている。見張り台が二つ。この柵は獣に対してのものではない。この辺りはたまに盗賊が来るのだ。
村の外から大声をかけ、長老を呼び出した。
痛む体を引きずりながら杖をついた長老が現れるまでそこで待った。その間も俺に近づこうとする村の子供にそれ以上近づかないように怒鳴りつける。子供は俺の剣幕に火がついたように泣きわめく。
ようやく長老が現れたので、俺は口を開いた。
「長老。新しい遺跡を見つけた。未発見の隠し部屋だ」
それを聞いて長老の顔がほころぶ。その意味が分かったのだ。俺は足下に置いた荷物を指さした。
長老も元は凄腕の発掘屋だ。実を言えば俺の師匠でもある。
「だが悪いニュースが一つある。とっても悪いヤツだ。その遺跡の防御機構がまだ生きていた。酸素の無い部屋で蚊に刺された。ナノ・インセクト・マシーンだと思う」
長老の眼が大きく開いた。
「刺されたのか。それは間違いないのか」
「間違いない。刺されたのは二時間前。まだ熱も息切れも痛みも兆候はない」
「そこから動くな。その蚊は回収したのか?」
「荷物の中の黄色の布の中に保存してある。調べてくれ」
俺は自分の荷物からさらに後退した。
何事かと飛び出て来た村人全員を追い払うと、長老は手伝いを一人だけ選び、荷物を回収した。しばらく経ってからその手伝いが戻って来て、俺の指から血を一滴取っていった。
すでに夜になっていたが、俺は村の外に留まっていた。小さな火を焚いて、じっとそれに魅入る。
俺は発掘屋を始めて以来欠かさずにつけている日記帳を取り出し、今日の日付を埋めた。朝起きたときは一日の終わりにただ一行だけ成果無しと書くつもりだったのに、今やそこには多くのことを書く羽目になってしまった。
幸運の後の不運。希望の後の絶望。神とは何と残酷なものなのか。
そろそろ深夜にもなろうかと言う頃合いになってやっと長老が出てきて、俺を手招きした。
「ザジや。こっちにおいで」
ザジとは俺の名前だ。
「シロか?」俺は希望を込めて訊ねた。
皺だらけの長老の額にさらに皺が寄った。
「残念ながらクロだ。お前は今、ブランガ・ウイルスに感染している」
覚悟はしていたがそれでも衝撃だった。俺の膝から力が抜ける。
ブランガ・ウイルスは極めて感染力が高い致命的なウイルスだ。扱いを間違えれば村どころか王国ですら容易く滅ぼすと言われている。前文明崩壊に一役かった生物兵器の一つでもある。
あの隠し部屋の持ち主は、侵入者を所属する集団ごと滅ぼすつもりだったのだ。
「長老。それ以上近づくな」
俺はかろうじてそれだけ言った。
「構わんよ。ブランガは感染から再感染能力が働くまで二日ある。それまではお前さんの血でも飲まない限りは感染はせん」
長老は俺の手を取ると、村の中の自宅へと導いた。
長老の家はレア遺物が多く置かれている。どれも盗掘を生業とする村には必須のアイテムばかりだ。
テーブルの上には村に一つだけある永久灯がついている。実際にはたった千年間光るだけだから、後五百年で耐用年数は尽きる代物だ。
テーブルの上にはこれもレア物の自動顕微鏡が置かれ、その横の空中に浮かぶ干渉スクリーンに拡大映像が投影されている。
そこにはあの潰れた蚊が大きく映っている。こうして見ると、それは生物などではなく、硬化樹脂と微小金属パーツで組み上げられたロボットだ。人体が放つ赤外線を探知し、自らが持ち運ぶ微小カブセルの内容を相手に注入する。自我すら持たない自動殺戮機械。モノは小さいが、致命的であることは変わらない。
「お前にこう言わねばならないのは辛いのだが。ザジよ。明日の夜までには村を出て行って欲しい。ブランガは空気感染する。つまりお前さんがここに残れば三日後には村人全員が死のウイルスに感染することになる」
俺は頷いた。遺跡の罠にかかって滅んだ村や街はごまんとあるのだ。発掘屋になったときにこの覚悟はできている。
「長老。念のために確認するがブランガ・ウイルスの対抗薬は存在しなかったよな」
「昔はあった。だが今は儂の知る限りは帝都にすら無い」
長老の言葉は明確だ。そして今までに間違いを言ったことはない。
では決まりだ。となると今やるべきはたくさんある。
まずは身近な人々に別れを告げることだ。
結婚の予定は無かったが同棲をしていた女に別れを告げた。ひどく泣かれたがそれも今夜だけの話だろう。じきにまた良い人を見つけるだろう。なにぶん彼女は器量良しだ。
ブランガ・ウイルスの保菌者となった以上は残念ながらここで抱くわけにはいかないし、口づけも厳禁だ。それぐらいではうつらないはずだが危険は冒せない。
念のためにあの手伝いの者が俺の見張りについていたので、やりたくても出来ないのも本当だが。
続いて長老が俺をすぐに追い出さなかった理由に取り掛かる。例の遺跡の場所を地図に描き上げる。今やこの一枚の地図は千金の価値がある。あの倉庫の中にはまだまだたくさんの遺物があるのだ。このまま忘れ去るにはあまりにも惜しい。あの財宝のお陰で百年後にはこの村は大きな都市に成長することだろう。
それから俺は必要な道具を揃え始めた。次の日は朝から、村の中の色々なものを徴発させて貰った。支払いは俺が見つけた財宝から行われるので、事実上無制限だ。
あの遺跡にも行き、表示されたリストの中から必要そうなものを選ぶ。物資を集めているとまた首筋をチクリとやられた。だが今さら余分に刺されたところで何ほどのことでもない。
俺は機械蚊が出て来たスリットを見つけると、樹脂でそこを固めた。これで後から来る第二陣の連中は少しは楽ができるだろう。
夕方になると俺はそれらを総て背負って村の入口に立った。
二度と住み慣れたこの村を見ることはないのだ。その寂寥感が俺の胸を打った。
「ザジ。これからどうするんだ?」
幼馴染のマルクが俺に訊いた。念のため俺とはかなりの距離を取っている。
「天空の塔に行く」俺は答えた。別に隠す必要はない。
「塔だって!」マルクが俺の言葉を繰り返す。
「前から登ってみたかったんだ」
「無茶だ」そう言ってからマルクは言葉尻を濁した。「そうか。そういうことか」
「ああ、俺の命は後わずか。ならばあれに登って死ぬ。今さら無茶も何もないからな」
俺は背中のリュックを叩いた。
「じゃあな。みんな。達者でな」
村から徴発した馬の背に跨った。今の時代の馬は過去の馬とはちがう。高度な技術で遺伝子改造されているのだ。従順でタフでしかも丈夫で賢い。おまけに暗視能力まである。こいつに任せておけば闇夜の中でも過たず進むことができる。
こうして俺は村を後にした。
一人になってから己の運命を呪って秘かに泣いたのは秘密だ。誰にも俺を情けないなどとは言わせないぞ。
3)天空の塔へ
高い山に登って周囲を見渡せば、地上の大概の場所から天空の塔は見える。それは天の遥か高見へと登る銀色の塔だ。
それが創られた当時はこう呼ばれていた。
『軌道エレベータ』と。
その先端は五万キロメートル高空にまで達する。そこは地上と宇宙を結ぶ橋の一方の端であり、また宇宙に下ろされた錘でもある。最先端には展望台が設けられ、宇宙と地上を同時に見下ろすことができると言われている。
その中を走るエレベータは当の昔に停止しており、今ではそれを修復できる者はいない。だが永久素材とまだかろうじて動いているらしい平衡自律システムが塔を直立させたままでいる。
世界で一番高い塔、あるいは宇宙の深淵深くに下ろされた蜘蛛の糸。それが天空の塔だ。
村に数頭しかいない馬を長老は俺に快く譲ってくれた。まあ俺が持ち帰った遺物に比べれば大した価値があるわけではないのだが。おかげで道が捗る。馬が手に入らなければ、天空の塔に登るどころか、旅の途中で病気で死んでいただろう。
寂れた道をいくつか辿っている内に大きな街道に出た。とは言え、人通りがあるわけではない。たまにキャラバンの連中が通りかかるだけだ。地球の人口はすでに枯れかけている。
人影を見たときは迂回をした。すでに感染から三日。俺の体の周辺には死のウイルスが散布されているはずだからだ。
ブランガ・ウイルスについては村にたった一つ残っていた知識球でまた調べておいた。
感染より三日で再感染可能となり、発病までは一週間、そして死亡までは平均二週間。空気感染し致死率は99%を越える。極めて厄介で、たった一種類の特効薬以外は一切効かない。そしてその特効薬が存在したのは五百年も前の話になる。
もしまたこれが流行れば、今度こそ人類は息の根を止められてしまう。
たった一つ良い点は人間以外の生物にはまったく感染しないこと。そういう風に設計された人工ウイルスなのだ。
走り続けるにつれ天空の塔は徐々に大きくなっていった。この地上に残った中でも最大級の遺跡なのだが、思ったよりこの塔を訪れる人間は少ない。それはどこからでも見えるから、近くで見る必要が無いからだろうと俺は思っている。それほど当たり前に周囲の景色の中にあるのがこの塔なのだ。
右手に見えていた海が森の風景に覆い隠され、その森も尽きると荒野だ。街道も寂れてところどころ草に覆われるようになる。重要な道路は前文明の作った永久素材の一種でできているが、その上に積もった土埃の上に草が生えるのは防げない。
俺は草に足を取られないように馬の速度を少し落として進んだ。
天空の塔の周囲にはちょっとした大きさの廃墟があちらこちらに無残な姿をさらしている。かっては繁栄した都市だったのだろう。まずコンクリートの建物の上に植物が侵食し、その次には上に盛り上がるように繁茂する。そしてそういう所は最後には例外なく鳥の楽園となる。
迂闊に近づくのは厳禁だ。鳥によっては子育ての時期には近づいた者を集団で攻撃する恐れがある。そういった中には戦争目的で遺伝子改造された鳥もいて、これらの場合は間違いなく命に係わることになる。
もう一日経って、ようやく天空の塔の根本に着いた。
4)天空の塔基部
天空の塔の基部は巨大な重量を誇る錘となっている。岩盤に直接埋め込まれた基部は天空遥か先の展望台の重量と綱引きをしているのだ。
五百年前には大いに賑わっていたこの場所は今は人気がない。言ってしまえばこれは廃墟ですらない。どちらかと言えば雄大な大自然の奇跡というのが正解だ。大きな滝や砂漠の中のオアシスといった位置づけだ。
地球のほぼ半分から見ることができる偉大なる人類が残したモニュメント。それが天空の塔だ。いつの日か、他の太陽系から訪れた者が最初に見るのがこの塔であることは間違いがない。
俺は長い間これを登るのを夢見ていた。そのために登山のトレーニングまで積んでいたんだぜ。でもこの夢はきっと一生叶えることなく終わるのだとも思っていた。日々の探検に明け暮れ、夢を見るもそれに進むことなく、やがて衰え、今度は長老と呼ばれる身分になる。そして死ぬときにああ、あの夢を叶えておけば良かったと、そう呟くのだと、なかば諦めかけていた。
それがこんな形で実現することとなろうとは。神様は慈悲に溢れていて、そして同時に限りなく残酷だ。空を飛びたいと願ったものを、大砲で打ち上げるような無茶なことを成さる。
塔の基部はなだらかな丘となっている。丘は永久素材でできていてその上に土が積もって木が生えている形だ。高価な永久素材をふんだんと使っていることで、この天空の塔の当時の価値が分かる。さすがに人類の夢と希望のシンボルである。
その木々の中心を抜けてようやく天空の塔の外壁にたどり着いた。壁にそって馬を走らせるとやがて本来の塔への入口が見えて来た。入口には設計段階から扉は設けられてはいない。
俺はそこで馬から降りると馬の装備を剥がした。
「ここでお前は自由だ。これからは好きに生きろ」
実際にはこの馬はどこか人間のいる場所を探し出してそこで面倒を見てもらうことになるだろう。人間と共存するように遺伝子が組まれているので基本的に野生には戻らない。
馬の尻に一鞭くれて走り去るその後ろ姿を見送る。手近の村にたどり着くまでは何日もある。ブランガ・ウイルスは人間の体外に出て一日で消滅する。この馬からウイルスが広がることはない。
俺は入口をくぐり、塔の中へと足を踏み入れた。
永久ペンライトは持っていたが、それでも用意してきた松明を使った。使い慣れたものの方が安心感がある。
塔の中心を通っているのは塔本体とも言える超単分子で構成されたロープだ。これらは全部で五本のロープで構成されている。一本のロープは蜘蛛の糸よりも細い繊維が千本合わさって作られている。この全長五万キロある繊維は一本まるごとが一つの分子として構成されている。全体を作り上げる原子の最外殻電子がすべて振動共有状態にあり、繊維を切るためにはこの巨大単分子全体を破壊するだけのエネルギーが必要になる。結果としてその細い一本で数百トンの加重に耐える能力がある。
これらはすべて知識球から得た知識だ。もっとも知識だけあってもそれを再現できるだけの資源も技術力も人口も無いのが今の人類の現状なのだが。言ってしまえば知識球の知識は魔法みたいなもので、魔法の存在は知っていても、それを使える肝心の魔法使いがいないようなものだ。
その超単分子のロープの周囲を軌道エレベータが上下するための空間があり、そのさらに外側を永久素材で作り上げた円筒が覆っている。
電力が無いので軌道エレベータは使えない。だがこの円筒外殻のすぐ内側を螺旋階段が通っている。これは軌道エレベータの保守用であるが、もともとの設計にこれが取り入れられたのはあくまでも当時の法律的な問題だと何かで読んだ記憶がある。
俺がこれから登らないといけないのはこの階段だ。高さは五万キロメートル。螺旋階段の全長はどのぐらいあるのだろう。
そこまで考えて少しだけ後悔した。もっと楽な死に場所があったはずなのだが。
それでも俺はこれを登るのだ。
覚悟と共に俺は最初の一段に足をかけた。
一度螺旋階段を登り始めると松明は不要だということが分かった。外殻のところどころが透明になっていて、外部から光が入るのだ。透明な永久素材なんて初めて見たと白状しよう。
螺旋階段を一定の高さ登ると天井に突き当たった。
螺旋階段の突き当りがドアになっていてそこで各階が分離されている。ドアは自動では開かなかったが、しばらく調べて、手動で動かせることが分かった。過去の技術者たちは塔の電力が消失したときのことまで考えていたようであり、そのことに俺は感謝した。
ハンドルを回して扉を少しづつ開ける。開いた扉から風が吹き出し、一瞬過去の記憶が蘇って、俺は慌てて息を止めた。手首のチェッカーを覗きこみ、ごく普通の大気成分であることを確認してから溜めていた息を大きく吐いた。
何のことはない。天空の塔の各階は気密ブロックになっているのだ。
扉を抜け、次の階に進む。
気密ブロックを五つ抜けた所で夜になった。小さな焚火を焚いて夜を過ごす。
この大きさの円筒空間ならば内部で火を焚いても大した問題にはならないとの判断だ。
小さな永久ペンライトを点けて口に加え、手元を照らす。これはあの遺跡から持って来た遺物の一つだ。この種の遺物は持ち運びが簡単でしかも結構な値で売れるので真っ先に回収される対象となる。
日記帳に発熱ペンで今日の出来事を記す。これらも遺物の類で、結構な値がした代物だ。日記をつけるのは冒険者になって以来の習慣で、日記帳はすでに八割ほどが小さな字と絵で埋まっている。最後は自分の死を記すことでこの冒険日記は終わるのだと理解していた。誰が読むというわけではないが、それでも自分の人生の全てがこれに詰まっていると思うと、この習慣を止める気は無かった。
携帯食を齧り、水を飲む。この塔の中に水があってくれれば良いがと思った。水は重い。だからあまり大量に持ち運べない。そして食料は二週間は無くても何とかなるが、水が無ければ三日で死ぬことになる。だがここから先は賭けだ。賭けることを恐れていては何も進みはしない。
朝と共に次の工程が始まった。各ブロックはほぼ百メートルの高さ毎に区切られている。
その内、新しいブロックのドアを開けるたびに、吹き出す風が強く長くなることに気づき、しばらく考えた後にその理由に気づいた。
気圧だ。各ブロックは一気圧に与圧して封鎖されている。そのブロックの扉を総て開いてここまで来ている以上、空気はそれ自体の重さで下の階へと流れ続け、高度にあった本来の気圧に戻る。高い位置にあるブロックほどその傾向は強くなる。つまりこのままでは塔の中の気圧は塔の外の気圧と等しくなってしまう。これはまずい。
それが分かって以来、ブロックを抜けた後は扉を必ず閉め直すようにした。
下手をすれば塔の上に到達する前に真空の中に飛び込む羽目になっただろうと思うと、ぞっとした。
そして俺はついに高度八千メートルに達した。
そこでは塔の壁に大穴が開いて螺旋階段が完全に崩壊していた。
5)大穴
望遠鏡はこの時代にも僅かながら存在する。だから天空の塔のこの部分に大きな傷があることは分かっていた。
永久素材のはずの塔の外殻に大穴を開けた原因が何かは想像の域を出ない。その中でも有力視されていたのは隕石の衝突説、そしてもう一つは世界崩壊戦争末期で使用された兵器である荷電粒子による砲撃だった。
ここまで来て見ると荷電粒子説が正しいように思えた。塔の外壁の端は何かの高熱で溶かされていたからだ。数千度の熱でもびくともしない永久素材を熔かすとはいったいどんな兵器なのだろう。想像すると身が震えた。文明崩壊にも良い点があるとすれば、今は世界のどこにもそんなものは残っていないということだ。
ブロックを封じる扉を開け始めた段階で、風が流れ込む替わりに吹き出し始めたので、俺は大穴に到達したことを知った。慌てて簡易酸素マスクをつけると、慎重に扉を開いて行く。しばらくその場に留まり、ブロック内の空気が十分に逃げるのを待ってから改めて扉を大きく開く。でなければ風の勢いに押されて塔の外へ吹き飛ばされてしまっただろう。
気圧は地上の三割というところか。酸素マスクが無ければ身動きも取れなくなるところだ。気温は零度付近。もの凄く寒い。
あの遺跡から防寒服を見つけて手に入れてはいたが、それでも寒い。できれば電熱機能付きの防寒服が欲しかったが、リストによるとそれは幾重にも積み重なったパレットの下にあり、取り出せなかったのだ。
ありったけの元気を搾りだし、荷物から登攀のための道具を出す。
螺旋階段は崩壊しているから、『中』、つまり軌道エレベータシャフトの横の壁を登るか、あるいは『外』、つまり塔外殻の外側を登るかのどちらかになる。
当然俺の選択は『中』だ。
『外』は眼下に八千メートルの垂直の壁を見ながらの登攀になるので、さすがに避けたい。誰だってそう思うだろ?
頭上の半分削られた壁を見る。超兵器の傷は、塔外殻だけではなく、軌道エレベータシャフトも削っている。それどころか、もしやその内部の芯である超単分子ロープにまで被害を与えている可能性があった。
この天空の塔が今も立ち続けているのは奇跡に違いない。ひとたびこの超ロープが切れたりすれば、塔の半分は地上に崩れ落ちて大災害を引き起こすことになる。
登る前にここで休憩を取ることにした。
携帯食を齧る。もう一週間も携帯食だけだ。もしここで一杯のシチューを俺に差し出すなら、代わりにこの汚れた魂を差し出してもよい。本気でそう悪魔に願ってみたが、悪魔は現れなかった。
替わりに俺の鼻から一滴の血が流れ落ちて簡易酸素マスクの中を鉄の匂いで満たした。軽く咳も出始めた。
これが祈りに対する答えか。ついにブランガ・ウイルスの発症が始まったのだ。
ならばぐずぐずしている暇はない。症状は激しくなれど治まるはずが無いからだ。これより先は死神のカウントダウンは容赦なく進む。
内壁の下に立ち、上を見つめる。
そのとき、俺の横に置いておいたリュックにぶら下げていたコッヘルが、金属音と共にはじけ飛んだ。
とっさに俺は横に転がり、伏せたまま周囲を見回した。
最初は銃撃かと思った。天空の塔の内部に何らかの防御設備があってそれがまだ生きていたのだと。だが次の攻撃は来なかった。
恐る恐る手を伸ばして転がったコッヘルの破片を取り上げる。綺麗に二つに切断されている。切断面に指を這わす。かすかに熱を感じる。
伏せたままごろりと上を向いた。耳を澄ませる。今まで外から吹き込む風の音に紛れて聞き取れなかったが、微かに何かが風を切る音がした。それも一つではない。無数の見えない何かがそこにある。
コッヘルの破片を上に向けて投げ上げる。
一回。二回。そして三回目でコッヘルは何かに打たれまた真っ二つにされた。
それで何が起きているのかが分かった。
過去に塔を破壊した攻撃は超単分子のロープも傷つけていた。切れた超単分子の繊維の端は自由になり、風に吹かれて振動する。
細すぎて目には見えず、自ら切れるには丈夫過ぎ、触れた物を切断するだけの鋭利さがそれにはある。
超単分子の目に見えない高速の刃。それが俺の頭の上を無数に踊っている。
ということは『中』は登れない。登ろうとすれば細かく切断されてひき肉になる。
俺はずるずると床を這いずり、外壁の大穴へと向かった。
永久素材にはハーケンは打ち込めない。それほど丈夫なのだ。だから俺が持って来たのは特製のニカワだ。
このニカワはあの倉庫にあった特殊素材の一つで、水分を吸収すると物凄い粘着力を発揮するという代物だ。普通の岸壁を登るにはまったくの無力なのだが、これを使えば永久素材の壁にも張り付くことができる。
最初の一つは外殻手前ギリギリに設置する。薄くて小さな板にニカワを塗り、顔のマスクをずらして息を吹きかけると、壁に押し付けて接着する。板は引っ張ってもビクともしない。
うん、行けそうだ。
板につけてある金具にロープを通して命綱とする。
荷物の大部分とはここでお別れだ。持っていくのは冒険日記と発熱ペン。携帯食料は1個だけ残してその場で全部食った。水は水筒一本だけ持ち、残りはできる限り飲んだ。最後はカンフル剤だ。これは体に大変によろしくない色々な成分を含んだアンプル剤で、一口飲めば疲れは吹き飛ぶというヤバさこの上ない代物だ。
ぐっと一気に一本飲むと、ほどなく疲労も寒さも感じなくなった。体の奥底に火がついたような感じがする。
それから元気を出した俺は外壁に乗り出した。
足下遥かに緑と茶のまだら模様の大地が見えた。下腹がきゅんとして一瞬パニックになりかけたが、訓練を思い出して、すぐに落ち着いた。俺はこのために長い間訓練して来たのだ。
風は恐ろしく強い。気を抜くと塔から引きはがされてロープで宙に浮かぶことになりそうだ。それだけは決してやってはいけないことだ。
手の届く限り上にある永久素材の壁を、棒の先に巻き付けた布で表面を磨き、ロープを通した例の板を張り付ける。
全体重をそれにかけ、体は横に寝かせた形で数歩上に向けて歩く。コツは塔の壁を地面だと思い込むことだ。
ロープにすべての体重を預け、本能に逆らって壁から体を離せば離すほど、登攀は楽になる。
一歩前進。そこでまた次の板を取り出し、ニカワを塗り、白い息を吹きかけて、上に張り付ける。
無茶苦茶だ。ニカワだけが俺の命を支える。危うい綱渡りのような登攀劇。だがこれは今のところはうまく行っている。
頭の後ろの光景は心の中から追い出した。
一枚、また一枚と上へ進む。途中疲れると、ロープにぶら下がったまま休む。一度に生きているロープは三本。例え二本まで外れてもまだ最後の一本がある。それだけが心の支えだ。
狙いはこの先にあるはずの外壁のメンテハッチだ。この天空の塔が活動していた時代にはそこから補修用のロボットが出入りをしていたはずだ。螺旋階段の中にあるメンテ用の分岐通路の位置からだいたいの場所は理解していた。もう少しでそこに届く。
次の一枚を貼り、先に進む。残りの板は後二枚。伸ばした手で外壁を探る。メンテハッチはこの辺りにあるはず。
無い。焦るな。俺。大丈夫だ。自分の考えを信じろ。
次の一枚をさらに先に貼り、そこに移動する。周囲を触りまくり、メンテハッチの隙間を探す。
ついに残りの板が一枚になってしまった。メンテハッチは上か、それとも左か。
しばらく悩んだ末に最後の一枚を取り出した。息を吹きかけようとして代わりに血しぶきを吹き付けてしまった。
ウイルスが暴れ始めている。ここで悩もうがどうしようが俺の命の終わりは容赦なく近づいている。
左と決めて貼り付けた。素早く体重をかけてそちらに移動する。
壁面を触る。伸ばした指先にかすかなひっかかりが感じ取れた。手袋越しだと確実ではないが何度も撫でている内に確信した。
有難いことに壁面のギミックの構造はどれも共通化されている。手動操作パネルの上をハンマーで強く叩くと、ハンドルが飛び出した。
寒風が吹きつける中で必死でハンドルを回すと、そこにあると気づかなかった扉が少しづつ開き始める。
扉は少し遠い。手を伸ばしたが届かない。
上を見る。どこまでも青空へと伸び上がる塔が目に入る。まるで空に落ちているような錯覚へと陥ってしまう。
下を見る。緑と茶色のまだらの大地がどこまでも広がっている。遥か下に雲が流れている。
その二つの深淵の境目が見渡す限りの地平線となって周囲に広がっている。
これが生きている間に見る最後の景色だと覚悟した。
何故か笑いがこみあげてきて、俺は息を殺して笑った。大声でも良かったが、それをやると血を吐くのではないかと恐れた。
可笑しくない。なのに可笑しい。笑える状況ではない。でも笑ってしまう。
人間とは案外こういう狂った生物なのだなと思うと、心が落ち着いた。狂った猿が大きな木を登る。ただ猿であるという理由から。それが人生の真理なのだと、ここに来て気づいた。
命綱のロープを二本解除して、たった今貼り付けた最後の板に結び付けたロープだけにする。それにぶら下がったまま体を振り、手を伸ばす。ゆっくりとだ。いかに強力な接着力を誇るニカワだろうが限界はある。もしこの最後の板が剥がれたら、地面まで約八分間の落下が始まる。人生を楽しむには短いが、祈りを捧げるだけの時間は充分にあるはずだ。
ぐんと反動をつけて体を振り出した。強風が背中を後押しする。
伸ばした手が扉の隙間にかかるのと、背後でメリメリと音がするのが同時だった。ニカワと壁面の間に血しぶきが入ったお陰で接着力が低下したのか。
死力を尽くして体を引き上げ、扉の中に転がり込む。後ろへと引き戻して来るロープのフックを叩いて体から外すと、それは風に引かれて扉の外に吸い込まれていった。
しばらく荒い息をつき、ひたすら体力の回復を待つ。ときたま咳が出て、少しだけ周囲に血が飛び散った。この血の中にはブランガ・ウイルスが無数に含まれているのだろうなとぼんやり思った。俺の体の半分は今や死のウイルスでできている。
ようやく起き上がれるようになったのでメンテハッチ内を奥へと進む。内部の扉を開くとそこにはまたいつもと変わらぬ螺旋階段が続いていた。損傷部位を越えたということだ。
そのまま螺旋階段を登り、次のブロックに到達する。扉を開けると開いた隙間から風が勢いよく噴き出してくる。風が弱まるのを待って中に這いこみ、再び扉をロックする。
二つほどさらにブロックを進むと、気圧が戻って来た。簡易酸素マスクの酸素も残り少なくなっていたのでほっとした。すでに高度は一万キロメートルに達している。ここより上で外殻の気密が破れていれば、酸素マスクのある無しに関わらずそこより先には進めなくなる。真空中では人間の体は沸騰するからだ。
気力と体力を振り絞りさらに五つのブロックを進んだ。
最後の携帯食を齧り、最後の水を飲む。気分が悪いのは高山病のせいなのか、それともウイルスのせいか。ここまでの経緯を日記に書き込み、ポケットに戻す。
与圧はされているが温度だけはどうにもならない。寒さに震えながら俺は眠りについた。
6)天空のテラス
高度一万二千メートル。水を見つけた。
このブロックはメンテナンス用途に特化されている。今では動かなくなった修復ロボットの集団が壁のくぼみに収まっている。
水が封入されたタンクがいくつかあった。どうやら外部の薄い大気から水を収集して蓄積する機構が存在しているようだ。水は電気分解して溶接用ガスの生成などにも使える万能素材だからか。
顔を水面に突っ込んで、心行くまで飲んだ。純水だ。味は無かったが今までにこれほど旨いものは飲んだことがない。何らかの熱源が容器の底に埋め込まれていて凍り付くのを防いでいるように思えた。
火照った顔に冷たい水が心地よい。ここの所、徐々に体温が上がり始めている。咳も頻繁に出るようになってきた。体の奥のどこかがひどく重く、むず痒い感じがする。
ブランガ・ウイルスは死ぬ直前までは比較的に体が動けるタイプのウイルスだ。こいつは罹患者が最後の最後までウイルスをまき散らすことができるようにと設計されている。
カンフル剤を飲み、気力を振り絞って体を起こす。無駄に休んでいてもこれ以上病状が回復することは無い。
高度一万五千メートル。壁の一部に完全に透明な部分を見つけた。どうやらここは中間展望室だ。湾曲した地平線が眼下に広がっている。色は青を基調として、それに纏わりついた大気が薄い膜となって被さっている。それと対比するかのように空の方は黒さが増し、その中に無数の星々の光が見えるような気がした。
足が重い。カンフル剤をまた飲む。
高度一万八千メートル。もう食料は無いので、水だけを喉に流し込む。元から食欲がなくなっているのが有難い。今日吐いた血は今までで一番多かった。目じりからも血が流れていることに気づいた。
だが俺はまだ登るのを止めない。
高度二万メートルを越えたので、祝いに水を一口飲み、最後のカンフル剤を飲み下した。
体が燃えるように熱い。今の俺の体の半分はブランガ・ウイルスでできているに違いない。頭がフラフラして、たまに意識が飛ぶ。重力はかなり小さくなっている。そうでなければとうの昔に動けなくなっていただろう。
小便の代わりに血が出たのには驚いた。
ふらつく体を気力で支える。
感染してから今日でどれだけの日数が経ったのだろうか。俺の命はあと何時間ぐらい持つ?
残り四万九千九百八十キロメートル。その数値に絶望した。
だがそれでも立ち止まる気はなかった。
高度二万五千メートル。四つん這いで進む。
そしてついに最後の階に辿りついた。
第二展望室。それがこの場所の正式名称だ。
螺旋階段はここで終わり、全体が透明な永久素材で覆われている。昼間ではあるが空はもう黒を基調とした一色で塗りつぶされている。横にある太陽が光を投げかけていて、俺の影を長く引き伸ばしている。地上から続く塔の最上段がここで、ここから先は軌道エレベータの超ケーブルが上へ向けて伸びているばかりだ。
この遥かな上空に錘の役をする展望テラスのブロックがあり、その遠心力で塔全体を引き上げている。そう知識球で学んだ。
俺の旅はここで終わりなのか。螺旋階段が途切れている以上、ここから上には登ることができない。
俺はこの展望室に設けられているベンチに座ると、残りの水の全てを飲み、ひどく重く感じるようになってしまった水筒を後ろに投げ捨てた。
あの遺跡を見逃して、代わりに静かな人生を得るという可能性もあっただろう。ある日いきなり女から妊娠を告げられて、大人しく村の農夫として生きる未来もあったのかも知れない。だが、結局、俺はここにいる。ここに居て、一人で死にかけている。
二週間前には想像もしなかった結末。
地上二万五千メートル。思えば遠くへ来たものだ。
俺は咳き込み、大量の血を吐き、記憶はそこで途切れる。どうやら意識を失ってしまったようだ。
目が覚めた。どのぐらいの間、気を失っていたのだろう。かすむ目で俺は時間を確かめた。
もう深夜だ。
それから気がついた。どうして夜なのに明るい?
夜空には星があるが、それどころじゃない明るさだ。
壁面が発光していた。つまりここには電力が供給されているのだ。天空の塔の最上部には太陽電池パネル群が展開されている。そこで作られた電力は塔の下へと送り込まれる。
あの大穴がそれを断ち切っていたのだ。大穴より上にある部分には、電力が供給され続けているということか。
もう俺は四つん這いでしか動けない。震える手で内部の壁面に触ってみる。微かに温かい。
何とか体を起こして操作パネルに触れる。
操作パネルが発光した。上向き矢印がついた部分をなぞる。
どこかで起きた振動が徐々に大きくなり近づいて来た。そして永遠が過ぎたと思える頃に、目の前の壁面が開いた。
天からの贈り物。人員運搬用軌道エレベータ。
俺はその中に転がり込んだ。気力を振り絞り、一際大きく作られている最上階ボタンの模様を叩く。この階より上に配置されている唯一のボタンだ。
静かに軌道エレベータは上昇を始めた。高度計の数値が驚くべき速度で上昇する。
途中で一瞬だけ上下が反転した。重力がゼロに近いので特に困ることは無かったが。
三十分が経過すると軌道エレベータはまた静かに減速を開始し、やがて止まった。奇妙な訛りに聞こえる標準語で最上階展望台天空のテラスとのアナウンスが行われた。
開いた扉から俺は転がり出た。
そこは宇宙の底だった。
床はすべて透明で、その足下に広がる漆黒の満天の中に無数の星々が輝いていた。重力は軌道エレベータの中のどこかで忘れ去られ、今や俺は僅かな遠心力のみで床へと押し付けられている。それもほんのわずかで、弱った体でも何とか動くことができる。
展望テラスの周囲には煌めく太陽電池パネルが広がっている。その幾つかは宇宙デブリの直撃を受けて破壊されていたが、残りはしぶとく生き残っていて天空の塔に電力を供給していた。
ここが終着点だ。
俺は床に設置されている椅子を一つ見つけ、そこに座り込んだ。もはや体は動かせない。病気は最終段階に進んでいる。
まだ生き残っていた電子機器が作動を始め、部屋の中に音楽を流し始めた。簡単にこの展望テラスの由来を述べ、本日の訪問客一名と誇らしげに宣言した。
恐ろしく愚直で馬鹿な機械ども。ここにいるのはただの違法な侵入者なのに。
俺は日記帳を取り出すと、ペンを探した。無い。どうやらどこかで落として来たらしい。
くそっ! 神様は何て意地悪なんだろう。
襟元に止めておいたピンを取り出すと、俺はそれを指に刺した。そしてその血とピンで最後の文章を書き留めた。
こうして誰にも知られることなく俺の冒険は終わりを告げた。
ここで宇宙を足下に踏んで、世界で一番高く、また同時に一番深い塔への登攀は五百年ぶりに完遂されたのだ。
7)来訪者たち
さらに長い長い年月が経過した。
ある日一隻の船が虚空を越えて飛んで来た。
重力をうまく操ると、その船は優美な動きで惑星から高くそびえる塔の頂点へと近づいた。
誘因場を形成し、一台の人造知性体を送り込む。今度は浸透場を形成すると、人造知性体は外壁をあたかもただの幻のように透過した。
天空テラスの中をつぶさに観察し、そこの椅子にたった一人座り続けていたこの星の支配種族らしき存在の死骸を発見した。
死骸が持っていた原始的な記録装置らしきもをすべて写し取り、天空テラスの死んだ電子機器から共鳴場を通じて吸い上げた知識を使って、その内容を解析した。
図表と文字の羅列。翻訳には十分な情報だった。
この惑星で何が起き、そしてどうなったのかを知った。死骸の来歴を知り、その冒険と挑戦とそして最後に得た勝利を知った。
船の知性との議論は異例なことに数秒もの長きに渡って続いた。
最終的に出された結論に従い、もう二台の人造知性体が派遣された。慎重な、そして敬虔な動作で、今や聖なるものと認定された死骸を船に収容すると超時空場エンジンを起動して虚空へと飛び去った。
銀河中心部にはこの銀河唯一の大記念館があり、銀河中から集められたコレクションが展示されている。
その一室に展示されたある原始部族の聖なる亡骸とその記録は、今でも銀河文明種族の間では高く評価され続けている。