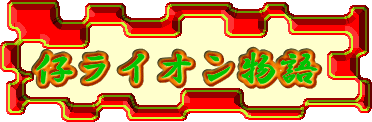
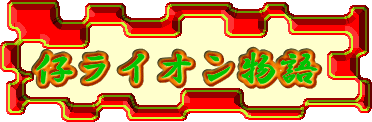
 父親(旦那)ライオン(母ライオン作)
父親(旦那)ライオン(母ライオン作)
ある日のことです。お母さんライオンはこう決心しました。
子供たちもずいぶんと大きくなったことだし、ここらで自立させなくては。
そうと決めれば、善は急げです。お母さんライオンはしぶる仔ライオンたちを巣穴から強引に引っ張りだすと、狩り場である草原へと連れていきました。
「見なさい」
狩り場にたむろするインパラの群を指さして、お母さんライオンは言いました。
「あそこにお昼ご飯がいます。お前たちの力だけでここで狩りをしてみなさい。捕まらなければ、当然お昼は抜きです」
「お弁当は無いの?」長女ライオンが聞きました。
「ありません」きっぱりとそう言ってのけると、お母さんライオンはその場から離れました。
「困ったな、どうしよう」末っ子の甘えん坊の仔ライオンが弱音を吐きました。
末っ子ライオンが喋るのは第三話以来です。無口な性格なのですが、きっと自分の影の薄さに嫌気がさしたのでしょう。
「まあ、何とかなるさ」元気一杯の次男坊ライオンが宣言しました。「そうだ。ここに落とし穴を掘ろう」
・・・子供というものは落とし穴を作るのが大好きです。たちまちみんなが賛成しました。
仔ライオンたちの手際が悪かったとは申しますまい。いえ、それどころか、彼らはとんでもなく立派で素晴らしい落とし穴を作ったのです。
見事に計算され尽くした深さ。底にびっしりと植え付けられた槍の穂先には、昆虫から抽出した致命的な猛毒が塗られています。落とし穴自体は偽装され、普通の地面と見分けがつきません。仔ライオンたちの匂いの跡も奇麗に隠され、その代わりの目印として、小さな、だけどとてもよく目立つ赤い花が植えられました。
もしこの場所にこの世に三人だけ存在すると言われる達人級落とし穴評論家がいたならば、感動に涙を流したことでしょう。それほどまでに見事な落とし穴でした。
効果はたちまちにして顕れ、通りがかりのインパラが一匹、かすかな悲鳴を上げながら、落とし穴の底へと落ちて行きました。重力とはインパラですら無視できないほどに偉大なものなのです。
わああい、やっったあ。仔ライオンたちは歓声を上げました。狩りは大成功です。
仔ライオンたちに呼ばれて獲物を見に来たお母さんライオンは、落とし穴にかかっているインパラの死体を見て目を剥きました
「とっても、とっても、とっても、よくないことです」お母さんライオンは人差し指を左右に振りながら、怖い目で仔ライオンたちを叱りつけました。
「卑しくもライオンが、落とし穴なんかを使って獲物を捕るなんて、許されないことです」
このお母さんライオンの剣幕に対して一斉に萎縮した仔ライオンたちの中で、次男坊ライオンだけがめげませんでした。母ライオンが放つ怒りの暴風に対して恐れげも無く立つと、精一杯に抗議しました。
「でも、獲物は捕れたよ!」
「獲物の問題ではありません。ライオンとしてのプライドの問題です」
ぴしゃりとお母さんライオンは言ってのけました。
「恥というものを知りなさい」
またもや仔ライオンたちは平原に放り出されてしまいました。
「困ったなあ。どうしよう」長男ライオンが言いました。
「何言っているのよ。獲物を追って、噛みついて、殺して、食べるのよ!」
長女ライオンが指摘しました。それからみんなでげんなりとしました。
「とても原始的なやり方だ」
末っ子ライオンが冷静な声で指摘します。彼は最近、古いスタートレックの再再再再再放送を見ていて、ミスタースポックに影響を受けているのです。
「じゃあ、どうすればいいんだ」
長男ライオンが嘆息しました。
今度も答えを出したのは次男坊ライオンでした。
作戦は大成功と言っても良かったでしょう。
突撃部隊役の2匹の仔ライオンはインパラの群の側面を襲いました。大口径の機関銃がけたたましい音を立てます。煙幕グレネード弾が発射され、怒号と悲鳴の交差する中、インパラの群はパニックになって逃げ出します。そこを、伏兵役の仔ライオンが飛び出し、派手な火炎放射器の炎で、インパラの逃げ道を塞ぎながら巧妙に誘導していきます。最後に待ちかまえているのは、安全そうに見える逃げ道に仕掛けられた対インパラ地雷です。次男坊ライオンがスイッチを入れると、地雷が破裂し無数の鉄片が空中を隙間なく満たします。その無慈悲な死の矢は、逃げ遅れたインパラたちを引き裂いてゆきます。
勝負はわずかに数秒で片が付きました。
「やったあ!」
うずたかく積まれたインパラの死体の山の上で、草原迷彩服を着た次男坊ライオンが喜びの叫びを上げました。
「大戦果だね」末っ子ライオンが感想を述べます。
「あたし、ママを呼んで来る」
長女ライオンが報告に走りました。
呼ばれてやって来たお母さんライオンは、インパラの死体の山を見て、白目を剥きました。
「絶対に! 絶対に! 絶対に! やってはいけないことです」
仔ライオンたちが思わずたじたじとなるほどの剣幕でお母さんライオンは怒りました。
「人間の武器を使うなんて。人間の軍隊を真似るなんて。あなたたち、ライオンとしてのアイデンティティはどこにやったの!?」
今度こそ褒められると思っていた仔ライオンたちはしゅんとなりました。
「とにかく」
激怒の印を自分の額に刻んだまま、お母さんライオンは宣言しました。
「武器の類を使うことは許しません。落とし穴も駄目。あなたたちが、きちんとした、正式の、ライオンとしての誇りを持った狩りをするまで、家に帰ってはいけません」
お母さんライオンが去ると、仔ライオンたちはまた頭を付き合わせて相談しました。
「どうしよう」長男ライオンがつぶやきました。
「もう、疲れたようう」末っ子ライオンがみんなの気持ちを代弁しました。
「そうだ、こうしよう」次男坊ライオンが言いました。
すべての仔ライオンの冷たい視線が次男坊ライオンに集中しました。きっとまたとんでもないアイデアを出すのだろうなああ、とはみんなが思っていましたが、それでも疲れていたのでその意見だけは聞いてやろうとも考えていたのです。
そんなみんなの思惑には気づかずに、次男坊ライオンは携帯電話をどこからか引きずり出しました。それと一緒に、宅配ピザのチラシもです。
「そんなもの使ってどうするのよ」
長女ライオンが懸念のこもった声で詰問しました。
「ピザを頼むのさ」
携帯電話のボタンを押しながら、次男坊ライオンは答えました。
「ピザ!? そんなもの頼んでどうするんだ?」とは長男ライオン。
「まあ、黙って見ていろって」
次男坊ライオンはみんなを牽制して黙らせると、電話に話しかけました。
「あ、宅配ピザ? 一つ聞きたいのだけど、ピザのトッピングにインパラを一匹ってできます?」
さあ、後はピザ屋がインパラを載せたピザを持ってやってくるのを待つだけです。ピザはすっかりと食べてしまって、残ったインパラだけを家に持って帰ればいいのです。
何という素敵で自堕落なアイデア!
全員が待っている所に、やがて藪をがさがささせて、何者かが近づいて来ました。
「遅いよ! ずいぶん待ったんだぜ!」
次男坊ライオンがそう叫ぶと、藪から顔を出したお母さんライオンとまともに向き合ってしまいました。
「そうかい。そいつは悪かったね」
抑えこんだ激怒を声の裏側に隠したまま、お母さんライオンは肩からまだ気絶したままのピザの配達員を下ろしました。
「獲物を待ち伏せしていたらこいつが引っかかってね」
ぞっとするほど冷たい声で、お母さんライオンは続けました。
「こんな所に、人間がいるなんて珍しいからね」
その指が伸びると、何かを言いかけてた次男坊ライオンの言葉を封じました。
「ごまかそうとしたって無駄だよ。こいつから全部訊きだしたんだからね」
どうやって訊きだしたのかその方法は説明しませんでしたし、仔ライオンたちも敢えて尋ねようとはしませんでした。燃えさかる炎の中に手を突っ込んだらどうなるかみんな良く知っていたのです。
だけども、全員の予想を裏切っていきなりお母さんライオンは泣き出しました。
「お前たち、何てことをしてくれたんだい。ライオンが宅配ピザを頼んだなんてご近所に知れたら、もうここには住めなくなるんだよ。文明化されたライオン一家なんて、シャレにだってなりゃしない」
これには仔ライオンたちもまいりました。母ライオンが泣きだすなんて初めてです。どう謝っていいものか、どの仔ライオンも地面を睨んでうろうろしています。
「もう、いい。狩りはいいからお前たちは家に帰りなさい。もうすっかり大人だと思っていたけど、まだまだ子供だったんだね。きちんとしたライオンのプライドを覚えるまで、家でまたお勉強だ」
お母さんライオンはそう命令すると、ピザの配達員と次男坊ライオンが持っていた携帯電話、それに宅配ピザのチラシを持って草原に分け入りました。
お母さんライオンはこれからすべての証拠を隠滅するのです。文明の証拠さえ消してしまえば、また元の、素敵な野生のライオンの一家へと戻れるのです。
ちょっとばかり罪悪感を覚えながら、仔ライオンたちは懐かしの我が家へと戻りました。
その途中、お昼ご飯がまだなことに気づきました。
長女ライオンが群れから離れたインパラを一匹追跡し、残りの仔ライオンたちがそれを待ち伏せして鋭い牙の一撃で倒しました。骨も肉もすっかりと平らげて証拠を隠滅すると、何事も無かったかのように巣穴へと戻ります。
もちろん、仔ライオンたちはもう立派な大人なのです。でももうしばらくは子供でいて、この平穏な巣穴の中で、優雅で退屈な、そして二度とは戻ってこないだろう子供時代を、じっくりと楽しんでいたかったのです。