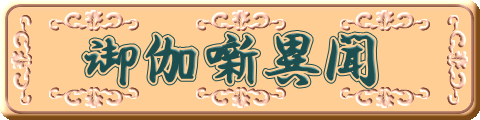
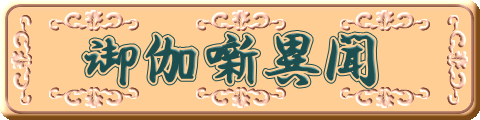
プロローグ)
『今は昔、竹取の翁といふ者ありけり』
竹林の中で見つけた黄金色に光る竹より生まれた女の子は輝夜姫とよばれた。
その子は見事に成長し、やがて見目麗しい娘へと変じた。炎に魅せられた蛾のように、大勢の求婚者が現れると彼女への愛を語るようになった。
彼女のために多くの高価な贈り物が集まり、貧しかった翁は一躍竹取の長者と呼ばれる存在へと成りあがった。しかし翁の勧めにも関わらず、輝夜姫は求婚者を悉く断り続けた。
その内に志の無い者は来なくなっていった。最後に残ったのは色好みといわれる五人の公達で、彼らは決して諦めることなく昼となく夜となく通ってきた。
五人の公達はその名を、石作皇子、車持皇子、右大臣阿倍御主人、大納言大伴御行、中納言石上麻呂といった。
この物語はその五人の公達の話である。
ある日、輝夜姫は五人の公達を一度に呼び出した。これら五人はほぼ毎日のように輝夜姫の元を訪れていたので、それはそう難しい話ではなかった。
「皆さま方の気持ちは嬉しく思います。されどこの身は一つ。故に皆さま方それぞれに課題をお出ししたいと思います。我が願いを叶えてくれた殿方に嫁ぎたいと思います」
それを聞き、公達たちは色めき立った。ついにこの美しい輝夜姫をこの手に抱くときが来たのだと。
輝夜姫は五枚の紙を取り、それにすらすらと美しい筆跡で何かを書きつけた。それを広げた布の下に隠すと、各自に一枚づつ取るように勧めた。
「お選びなさい。そしてそこに書かれたものを私に持って来てください」
いった何が書かれているのかと戦々恐々しながら、公達たちは抜き出した紙を開いた。
車持皇子には「蓬莱の玉の枝」
大納言大伴御行には「龍の首の珠」
右大臣阿倍御主人には「火鼠の裘」
中納言石上麻呂には「燕の産んだ子安貝」
石作皇子には「仏の御石の鉢」
「これは!」全員が一斉に声を上げた。
「蓬莱の球の枝とは何でござりましょう?」車持皇子が尋ねた。
「蓬莱山については知っておられますね」輝夜姫は言った。
「それはもちろん。中つ国の東に浮かぶ仙人が住むという島の名ですな」
「そこに生えているという木の枝でございます。その根は銀でできており、茎は金、そして珊瑚の葉に真珠の実が成っております」
「そのようなものが実在するのですか」
「実在しますとも。この私めが所望するものはすべて実在するものばかり」
車持皇子は少しばかり考えた。そのようなものならば職人に作らせれば何とかなるのではないかと。
「その枝は折り取りても枯れませぬ。故に土に植えれば大きく育ち花を咲かせます。それを持って本物の証としとうございます」
車持皇子の肩ががくりと落ちた。もしや自分が引いたこの紙は一番の外れではないかと思った。
「龍の首の珠とは何でござりましょう?」大納言大伴御行が尋ねた。
「龍が首につけている珠のことでございます。たまに手に持ち替えることもございまする」
輝夜姫は言った。
「それを私に取ってこいと? 危なくはございませぬか」
「もちろん大変に危険です。珠は龍の位を示すもの。つまりは龍王だけが持っておりまする」
「ううむ」大納言大伴御行はうなった。
「お止めになりまするか?」
大納言大伴御行は項垂れた。もしや姫は自分が嫌いなのではないかとも思った。
「火鼠の裘とは何でござりましょう?」右大臣阿倍御主人が尋ねた。
「火の中に棲むという火鼠の皮で作った布でございます。その布は火の中で燃えず、逆に綺麗になるというものでございます」
「そのような鼠が居るものでしょうか」
「私めはそれを見たことがありまする」
右大臣阿倍御主人は押し黙った。確か御帝がそのような布を持っていたと耳にしたことがある。だが輝夜姫を得るためにそれを借りだすことはまず無理とは判っていた。借りだすにはその理由を述べねばならず、またそうなれば好色なる御帝が輝夜姫に懸想することは確実と思えたからである。今はまだ輝夜姫の美貌については御帝の耳には届いていないし、お付きの者たちも極力噂が御帝の耳には届かぬようにしている。だがそれもいつまで持つことやら。
右大臣阿倍御主人は押し黙った。
「燕の産んだ子安貝とは何でござりましょう?」中納言石上麻呂が尋ねた。
「燕は我が子の成長を助ける目的で特別な子安貝を巣の中で産みます。その貝のことでございます」
「わかり申した。ただちに手に入れて参りましょう」
「本物の子安貝でなくてはいけませぬ。その辺りの浜辺に落ちているような普通の子安貝を差し出されれば、私は怒りましょうほどに」
姫に心の中を見透かされたような気がして、中納言石上麻呂は体を小さくした。
「仏の御石の鉢とは何でござりましょう?」石作皇子が尋ねた。
「お釈迦様がお使いになられたという托鉢鉢でございます。それは光り輝いていたと申します」
「そのようなもの、この世にありましょうか」
「おそらく天竺には」
輝夜姫は恐ろしいことを言い出した。
石作皇子の顔色が変わった。天竺への旅などまったくの無謀。隣の中つ国に行くだけでも三隻の船のうち二隻は遭難する。
「お嫌なら、その紙を破ってお帰りなさい」
輝夜姫が冷たく言い放ったので石作皇子は顔を青くした。
竹取長者の家を出ると、五人は頭を抱えた。
「なんという難題」
「どうすればよいと言うのか」
「もしやこれは姫が我らの求婚を断るための口実ではないか」
「いや、きっと我らが慌てふためく様を楽しんでおるに相違ない」
「何という女狐」
「我らを馬鹿にするにも程がある」
「いっそ皆で諦めるか」
「それはよい。そうしようではないか」
「うむ。姫のことは諦めるとしよう」
五人はそう言うと、他の者をこっそりと出し抜くために急いで帰路へとついた。
1)蓬莱の金銀珊瑚でできた枝。
車持皇子は頭を抱えていた。
蓬莱の木の枝だと? そのようなものがこの世にあるものか。
だが、輝夜姫のあの真っ白なうなじ。凛とした佇まい。一点の傷も無い滑らかなる肌。傾国という表現がぴったりくるほどの美貌。輝夜姫という名の芸術品が存在する以上、金銀珊瑚の枝もまた存在するはずであった。
真っ先に考えたのは、本物の金銀珊瑚で枝を偽造すること。一応輝夜姫には釘を刺されてはいたものの、それが根付かぬと気づかれるまではごまかせる。その間に輝夜姫との間に既成事実を作ってしまえばバレたとて何ほどのものでもない。
車持皇子は夜遅くに工芸の匠の頭の下を訪れた。しばらく話をしてからそれとなく水を向けたところ、喜んで金銀珊瑚の枝を作ってくれるとの色良い返事が貰えた。
それを聞いて車持皇子は内心小躍りした。ただし代金は前払いと続けて聞かされるまでは。考えてみれば当たり前のこと。それほどの金銀珊瑚の細工物、前払いでなければまず材料自体が揃わぬ。
次の日の夜には車持皇子が匠の頭を訪ねたことはすでに周囲で噂になっており、偽物を作る企ては敢え無く潰えた。
こうなっては実際に実物を手に入れる他は手が無い。
蓬莱島は中つ国の東の海上にあるという仙人たちの住まう島だ。ということは日の本からは南にあることになる。日の本でも金銀は算出するが珊瑚が生えることはないから、蓬莱島の枝に珊瑚が生るのは確かに理屈ではあっている。
車持皇子は船を仕立てて旅に出た。幸いにも遣唐使に伝手があり、長い長い時間がかかったが中つ国へと辿り着くことができた。
一緒に出た四隻の船の内の二隻が沈んだ。想像以上の長旅により旅費の大部分を使い果たし、車持皇子は相当みすぼらしい成りになっていた。金銀珊瑚の枝を贖うための余分な金子を持っていなければ、ここに辿り着くこともなく旅の途中でのたれ死んでいただろう。
問題はその金子をすでに旅費に使い果たしてしまっていること。これでどうやって金銀珊瑚の枝を買い求めよう。そしてまた日の本の国へどうやって帰るのか。
それ以上は考えるのを止め、車持皇子は周囲一帯で聞き込みをした。やがて海の上に蓬莱島が見えるという噂を聞きつけ、その場へと赴いた。
着いてみれば噂は本当で、海の向こうに小さな島が一つ燦然とした輝きに包まれて鎮座ましましていた。島の大部分は霧に包まれていたが、見える部分だけでもキラキラと何かが輝いている。
思わず海岸へと走りいでると、浜には一艘の小舟が乗り上げていた。これぞ天の助けとばかりに乗り込むと、小舟はギイギイときしみ音を立てながら、蓬莱の島目掛けて勝手に進み始めた。
はて、これは面妖な。櫂もないのにこの船はどうやって進んでいるのか、と呆れているうちに、やがて小舟は島に一つだけある桟橋へと着いた。
体の半分を覆う白い顎髭を生やした老人が一人、そこで待っていた。老人は車持皇子の顔を見ると声をかけて来た。
「よくぞ、ここまで参られた。弟子入り志願者じゃな。さあ、島に上がるがよい。そうともここが蓬莱島じゃ」
「ということは貴方は仙人さまで」
「うむ。まあ、当たりじゃ。さあ、こちらに来るがよい」
老人の後について島の中央に聳える蓬莱山に登ることになった。柔らかな緑と見たこともないような極彩色の鳥に囲まれて、何やら良い香りのする中を島の中央目掛けて進んだ。木々はやがて煌めく何かに置き換わっていった。それが金銀珊瑚でできていると知って車持皇子の心臓は高鳴った。背後を歩む車持皇子の物欲しげな視線を知ってか、案内をしていた仙人がどことなくおかしさを含んだ声で言った。
「欲しければ枝を取ってもよい。枝が取れたらそのまま帰ってもいいよ」
躊躇う理由はなかった。車持皇子は手を伸ばし、枝を一本折り取ろうとした。だがその華奢に見える枝はどれだけ力を込めてもびくともしない。
それを見て老人はカラカラと笑った。
「仙人としての修行をしない限り、お主が素手でここの枝を折り取ることはできぬというものよ。さあ、諦めてこっちへおいで」
老人につれて行かれた先には、この島には似つかわしくない粗末な小屋があった。
「今日からここでお前は修行をするのだ。修行を積んで位が上がれば、そのたびにより山の高い場所に移ることになる。蓬莱山の中腹に至った頃には、島の木の枝を折り取ることもできよう。そうなったら自由に枝を取って、家に帰ってよい」
それだけ言うと老人は姿を消した。
修行は水汲みであった。用意された瓶を持って泉に行き、水を汲んでは寝床の傍に置いてある大瓶の所まで運びそこに貯める。大瓶が一杯になると、どういう仕組か中味はまた空になり、最初から同じことが繰り返される。
この修業を初めて百日目、再び老人が現れると、次の庵へと案内してくれた。
今度は火炊きの修行であった。目の前で燃え盛る炎にうず高く積まれた薪を投げ込みながら、車持皇子は尋ねた。
「今度の修行はいつまで続くのですか。それと修行は後いくつあるのですか」
「そなたの修練しだいじゃが、まあ百日ほどじゃろう」老人は説明した。
「それと今のお前さんは弱丹生という見習いの位じゃ。この火の修行が終われば柔和生と言う位になる。すべての修行が終り、仙人になるには百七の位を経る必要がある」
心して励めとだけ言い残して老人は消えた。何としても逃げようと車持皇子は決意した。
だが、このまま逃げても時間を無駄にしただけだ。何としても、金銀珊瑚の枝を手に入れなくてはいけない。だが、素手で枝を折り取ることは叶わぬ。ならばどうすればよい?
答えの出ぬままに修行を続けた。また百日経つと老人が訪れ、次の小屋へと案内された。
次の修行は島に算出する丹砂の採掘であった。鋼のように硬い赤い石に鶴嘴を振り下ろす。手にマメができ、そのマメが潰れてまた次のマメができる。
さらに百日が経過する。今度は斧を渡されて、仙境ナナカマドの木を切らされた。切った枝は二番目の修行の小屋の外に積み上げておいた。
ふと思いついて、車持皇子はその斧で金銀珊瑚の枝を切ってみた。素手では折り取れぬその枝も、仙界の道具である斧に当たるとあっさりと切ることができた。
枝を手に取ってみると見た目よりもずっしりと重い。金の枝に、珊瑚と真珠がぶら下がっている。大粒の真珠の実がたわわに成ったそれは実に見事なものだった。残念ながら銀でできた根の部分はないが、これでも輝夜姫は喜ぶのではないかと思った。もちろん根が無くては根付くことはないはずだが、なにせ仙界の植物だ、案外にこれだけでも土に埋めれば根付くやもしれぬ。それに輝夜姫はどうあれ、竹取の長者の方はこの枝欲しさに輝夜姫を説得してくれるのではないか。そう思った。
壊れぬように慎重に枝を布で包むと、見つからぬ内にと島の船着き場へと走った。
桟橋に繋がれている幾つもの小舟はどれも同じに見えた。その舳先には何やら文字が彫られているが、そもそも仙界の文字など車持皇子に読めるわけがない。えいやと手近の小舟に飛び乗ると、もやい綱を解いた。船がゆらりと海流に乗って動き始める。
そのとき蓬莱島の桟橋に老人の姿が見えたが、仙人は別に船を止める素振りをするでもなく、静かに車持皇子を見つめるばかりであった。
来たときとは逆の光景を辿り、やがて小舟は海を渡り切ると浜へと着いた。
ここはどこだ。追っ手はかからぬか。さて、どうやって日の本へ帰ろう。輝夜姫はまだ待っていてくれているだろうか。さまざまな思いが車持皇子の胸中を交差した。
そこまで来て初めて、周囲が見慣れぬ光景であることに気づいた。
地面は土でもなく石畳でもない継ぎ目のない白い石の素材で埋め尽くされている。周囲の建物もすべて石作りで、むしろ木の建物は見当たらなかった。金物でできた車が幾つも転がっている。それを引くべき馬も牛もどこにも見当たらなかった。
外は日が暮れようとしていたが、その代わりに建物自体が奇妙な乳白色の光を放ち始めた。
その夕焼けの空に黒い何かが群れをなして飛んでいた。遠くで雷のような音がして、幾人かの人々が必死の形相でこちらへ向けて走って来た。どの人も見慣れぬ服装をしている。空を飛んでいた黒い何かが小さなホコリのようなものを空中に吐き出すと、それは地面へと落下し、大きな音と炎を立てて空を焦がし始めた。
あれは何だ?
この国にはあのような妖怪がいたのか。驚きとともにあちらこちらと彷徨った。やがて自分が元いた場所から、いや、元いた時代から大きく異なる場所に居ることを理解した。仙境の小舟はなにか分からぬ術で彼を遥か遠くへと運んでしまったのだ。
蓬莱島に戻ろうにもあの小舟はすでに無く、それから長い間探しはしたが、決して小舟が見つかることは無かった。
2)龍の首の珠
東海龍王。
唐の国の東の海を支配すると言われる龍の王様。そんな大物であればこそ、必ずや龍の珠を持っているはずと、大納言大伴御行は結論づけた。そうと決まれば愚図愚図はしていられなかった。首尾よく龍の珠を手に入れたとしても、他の求婚者より後になってしまえば意味が無いのだ。輝夜姫のあの美しい肢体が誰か他の男のものになってしまうことを考えると、大伴御行の心は嫉妬に燃え、その魂は焼け焦がれた。
何としても、自分が最初の一人でないといけない。
そのためには金に糸目などつけてはいられなかった。所領を担保に大金を借り、めぼしいもの総てを売り払って、一艘の大船を仕立て上げた。熟練の水夫を雇い、百戦錬磨の強者どもを呼び寄せた。敵は龍王。どれだけの軍備を揃えたとしても足りはしない。
ありったけのものを集めると、吉日を選んで船は出航した。船の舳先に立つは綺羅びやかな甲冑に身を包んだ大伴御行の姿があった。
船が出て四十と八日目。船はついに目的の海域へとたどり着いた。ここは土佐の沖合。波が荒れることで有名な場所だ。陰陽寮頭の話によると、この荒れた波の下に竜宮城が眠っているとのことであった。
竜宮城には招待された者しか入れぬ。だが、大伴御行の目的は竜宮城に入ることではなく、龍王に相まみえること。ならば話は簡単だ。
「東海龍王。東海龍王。ここにいるは大納言大伴御行なり。いざやその姿を見せたまえ」
船の上で大声でおらばった。
「姿を見せねば、東海龍王は大納言大伴御行を恐れて姿を隠したと天下に広めよう。その名ほどではない臆病者と罵り、あざけ笑ってみせようぞ!」
それを聞いて船の上にいた者たちは顔色を変えた。特に元より海の者たる水夫たちは。嵐と海の神である龍王を怒らせたら、陸へ戻ることはできぬ。
周囲の人間がこの大伴御行の蛮行を止める間も無く、大風が吹いた。海の表面がざわめき、波打ち、のたうち回った。深海の底の底から、何か大きなものが浮かび上がって来た。巨大なる顎、蘭蘭と光る眼、無数の鱗に覆われたその体。
東海龍王が出現した。その首に光る珠が一つ燦然と輝いている。
「弓を貸せ!」
大伴御行は叫ぶと、震えるお供の手から長弓を奪い取る。矢を一本つがえると、ひょうと放ってみせた。
矢は龍王の鋼の鱗に当たり、情けない音を立てながら、むなしく跳ね返った。
「何をしている。皆の者。矢を放て!」
大伴御行は背後を振り返り、皆が腰を抜かしてへたり込んでいるのを見て、唖然とした。
龍王の体が素早く動いた。船の帆を破り、甲板に穴を開け、舵を叩き砕き、ついでに水夫を数人海の中へと引きずり込むと、再び海の中へと消え去った。
龍王たるものその威容を見せた以上は、愚か者にいつまでもかかずりあってはおれぬ。
船が漂流した挙句、陸にたどり着くまでに十日ほどかかった。
陸につくとすぐに次の船を仕立てようとしたが、その前に噂は広がり、もはや水夫になろうとするものは誰もいなくなってしまった。屈強だったはずの剛の者たちもどこへとなり逃げてしまい、大伴御行は一人で孤立した。
ここで諦めてなるものか。大伴御行は決心した。脳裏に映るはあの美しき姫の姿。龍王に出会う所まではいけたのだ。あの首に掛かっていた龍の珠まではあとわずかだったのだから、諦めきれるわけがない。
今度は一人で扱える漁船を仕立てた。たった一人で船に乗り、恐らくは竜宮の真上であるはずの場所へと再び漕ぎついた。ところがいくら大音量で呼ばわっても、二度と龍王は出て来なかった。
「うぬ。あやつ。この私から逃げおって」
半分正解で半分誤解の言葉を吐くと、大伴御行は龍王を追った。この海にいないならば、きっと別の海に移ったに違いない。きっとまだ遠くには行っていないだろう。
そう信じた。
船は西へ西へと進んだ。関門海峡を過ぎ、荒れた日本海へと出た。そうして九州の西岸を南下し続けた。道々、龍王の居場所を尋ねながら。
二か月も経たぬうちにただでさえ乏しい路銀は尽きた。漁船は売り払い、代わりにその港に来ていた貿易船に乗った。水夫として雇われたのだ。生まれて初めて労働というものをした。最初はきつかったが、やがて厳しい労働にも慣れた。筋肉もつき、日に焼け、水夫の使う汚い言葉も覚えた。
それでも龍王は見つからなかった。
日本海の荒波を越えるのは恐ろしい体験だった。しかし彼はくじけなかった。
その内に日ノ本の国の言葉の通じぬ所にたどり着いた。苦労の末にそこの国の言葉も覚えた。何度もここで引き返そうとも考えたが、その度に脳裏に輝夜姫の芳しい姿が浮かんだ。整った顔に、すらりと伸びた手足。鈴を震わすような素敵な声に、優雅な仕草。それら総てが龍の首の珠一つで贖うことができるのだ。諦められるわけがない。
言葉は覚えた。覚えないと野垂れ死にだ。そうやって西へ西へと流れ続ける内に、新しく覚えた言葉の通じぬ所にたどり着く。またもや片言ながらも知らぬ言葉を覚えた。
そうこうしている内に、小さいながらも自分の船を持つようになった。貿易は儲かる。途中に待ち構える悪天候に海賊に悪辣な役人さえうまく避けるコツさえ掴めば。
船はやがて大きなものへと代わり、部下も増えた。それ以上大きな船が手に入らなくなると、今度は船の数を増やした。大船団をまとめあげ、あらゆる海を巡った。
それでも龍王は見つからなかった。
じきに行き合う国の王が深々と頭を下げるようになった。彼の率いる船団は伝説となり、一国の経済を左右するほどの財物を運ぶようになった。行き先は船団長以外はしかと分からず、ただ噂では龍が出没するという話があれば、ためらわずに出航するという話があった。
大きな船団の一番大きな船の舳先に立って、大伴御行は常に前を見つめていた。
大海原の先に伸び上がる竜巻を見ては龍ではないかと胸を高鳴らせ、見知らぬ陸地の影を見ては龍の隠れたる棲家ではないかと疑ったりもした。
船団はさらに大きくなり、背後に長い航跡を引く。それ自体がまるで大きな龍のように。青い海に白い跡を残して、ひたすらに進んだ。
凍てつく氷の海を。大声で叫ぶ嵐の中を。照り返す赤道の暑さの中を。潮と、風と、太陽が、大伴御行を鍛え上げていた。血に飢えた原住民と海賊たちと敵国の海軍が、大伴御行を磨き上げていた。
盛り上がった筋肉に見事に日に焼けた肌。背後に続く大船団はいずれも彼に無謬の忠誠を誓っている。
ある日、長い長い航海の後に、緑の大地に行き着いた。
優しい木々の匂いのする大地であった。大船を指示して浜に着くと、村人が恐る恐る近づいて来た。
「あんた達、あんな大きな船を引き連れて、どこから来なすったね?」
村長と思われる男が訪ねた。
知らない言葉。だが聞き覚えがある。思い出す。懐かしい故郷の言葉。
大伴御行は、はっと気づいた。龍を求めてひたすらに西へ西へと旅をしてきた。ギリシアなる賢者の国にて聞いたことがある。世界は丸いのだと。とすればこうして西へと旅を続ければ、いつかは、故郷、日の本の国へと着くのではないかと考えたことがある。
まさか事実だったとは。
龍は見つからなかった。だが代わりに天地を丸ごと買えるほどの財物を手に入れた。
姫は待っていてくれているのだろうか?
この財物で龍の宝珠の代わりと認めてくれるのだろうか?
だが、と大伴御行は思った。ここで姫の下に帰れば俺の旅は終わる。二度と再び航海に出ることはなくなるだろう。大伴御行は目の前に広がる緑の大地を見て、そして背後の青く果て無き海を見た。
両者を見比べ、考えた。俺が住むべき、いや、俺が棲むべき場所はどちらなのかと。
答えが出るまでに長くはかからなかった。
「出航だ!」
大納言大伴御行は部下に向けて叫んだ。
「龍を探しに行くぞ!」