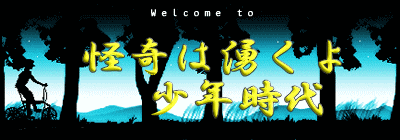
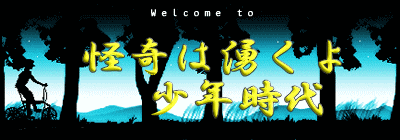
小学生低学年の頃、私は本州最南端の港町に住んでいた。アパートの前にはドブ川があり、さまざまなゴミが流れていた。眼の前の対岸にはクジラ肉の処理工場があり、捕鯨船が入港した日は川がクジラの血で真っ赤に染まるのが日常であった。
名も無きドブ川とは言うものの、多少の水量もあり、腐臭を放つというわけではないので、季節によってはボラの大群が遡上することもあった。悪ガキたちは発泡スチロールに棒切を差して軍艦に見立て、上流から流しては石をぶつけ撃沈を競う、などという遊びもやっていた。川と誇れるほど大きなものではないが、それでも遊び場としてはそれなりの役に立っていた。大人たちはただのドブ川として見向きもしなかったが。
ドブ川の両側は石垣となっていて上り下りできるようなところはない。そのまま海へと繋がっている。上流側は一部暗渠となっているが下流側は開けていた。
ある日の事、一匹の錆色の魚が川を上って来た。結構大きな、大ぶりの鯉ほどもある魚である。その魚は川縁の石垣に身を寄せるかのようにして、小学生の私の眼の前にいた。この水深の深さなら、長い取り網でも持ってくれば捕まえられるのでは無いかとも思ったが、あいにくとそんな便利なものは持っていない。何よりもドブ川で獲った魚を食べる気はなかった。さらに付け加えるならば、食べ物としての魚は嫌いであった。
周囲に誰もいなかったので、ただ一人、魚を上から眺めるだけでその日は終わった。
その魚のことは誰にも言わなかった。近所のガキ連中の中でのヒエラルキーは最低なので、言えばきっと誰かに取られて、私には触らせて貰えないことは明白だったからだ。特に私を虐めることに全力を傾けている兄は、私がそう従っているという理由だけで、あらゆる種類の妨害を仕掛けてくる人間だったから、この秘密は誰にも言わなかった。
次の日、覗き込んで見ると、魚はまだそこに居た。次の日も、またその次の日も。その時点で、魚は死んでいるのではないかと思った。そうでなければ動かない理由がつかない。
大きな目、意外と大きい錆色のウロコ。体をピンと伸ばし、上流に顔を向けて固まっている。海魚だろうか。そうでなければこの小さなドブ川の中でここまで大きくなるわけがない。こないだ上がって来たボラの一匹だろうか。あのときは大人たちが長い網を持ってきて何とか救い上げようとしていた。そこから逃れてきてここまで上がって来たのだろうか。
それからは毎日魚を監視するのが私の習慣となった。小学校に出かける途中で眺め、小学校から帰って来る途中で眺める。誰にも見られるわけにはいかない秘密の行動。
やがて、魚の輪郭がぼやけて来た。ついに腐ったのかと小学校で一番良いとお墨付きを貰った目を凝らしてみる。
腐ったのでも、崩れたのでも無い。全体に緑の藻が付き始めていたのである。当時は子供ではあったが、それでも死んだ魚は腐るものだと理解していたから、これは謎であった。
やがて藻は長く伸び、水流にたなびくようになった。おかしいおかしいと思いながら監視は続いた。
そしてある日突然気が付いた。
そこにあるのは、水に揺れる長い藻を生やした細長い石。その石は、じっと見つめていると、どことなく魚を連想させてしまう。
その石が元は魚であったことを、世界中でただ一人、私だけが知っている。