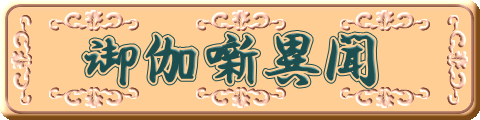
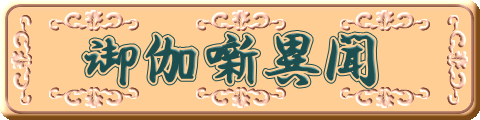
川上から大きな桃が流れてきてから二十年、ついに桃太郎は立派な若武者となり、鬼ヶ島へ鬼退治へ出かけることと相成った。
お爺さんは裏庭で育てた特別なキビからキビ粉を作り、それを各種の薬草と混ぜ合わせました。お婆さんがそれを小さめのキビ団子に仕上げて、袋いっぱいに詰めてくれました。
そのキビはお爺さんが都を追われる原因となったものです。
お爺さんは桃太郎に注意をしました。
「いいかい。桃太郎や。これを使って強そうな家来を集めるのだよ。一人につき一日に一個だけ与えるのだ。それ以上は駄目だよ。それとお前は決してこれを口にしてはいけないよ。お前が食べたらそれはそれは大変なことになる」
キビ団子はとても美味しそうな匂いを放っていたので桃太郎は残念に思いましたが、それでも言いつけを破ることはしないつもりでした。
とっても特別なキビ団子。これがこの話の主役となります。
奥深い山を五つ越えると平地に出ます。その手前の山の中で桃太郎はキジに出会いました。
「とても美味しそうな匂いがしますね。それを一つ私にくれませんか」
キジはそう提案しました。動物が人語を喋るのは異例のことですが、山奥での爺婆との三人暮らしだった桃太郎にはその辺りの常識はありません。
「これが欲しいのか?」
桃太郎はキビ団子を一つ、キジに差し出しました。
恐る恐るそれに口をつけたキジは一口食べるともう夢中です。瞬く間にすべて食べ尽くしてしまいました。こぼれた粉まで一つ残さず舐めとるとキジは懇願しました。
「お願いです。この素晴らしい団子をもう一つください」
桃太郎は首を横に振ります。
「この団子は一日に一個だけだ。それも俺の鬼退治についてくる者だけが貰える」
「では貴方についていきます」キジは即断しました。
一人と一匹は平地をさらに進み、街道へと行き着きました。
そこで桃太郎は一匹のイヌに纏わりつかれました。
「くんくん、旨そうな匂いがするぞ」
「お前もキビ団子が欲しいのか? 俺の鬼退治についてくるならやらないでもないぞ」
「もちろんついて行きますとも」
イヌはキビ団子を貰ったらすぐに逃げようと思っていたのです。
ところがそんな考えも、桃太郎の差し出したキビ団子を舌の上に載せた瞬間に吹き飛びます。桃太郎の肩の上では、キジがギラギラした欲望の眼差しで、イヌがキビ団子を食べるのを睨んでいました。
街道に沿ってさらに旅をすると海にたどり着くことになります。
そこでは海辺の松の上にサルが登っていて、足下のカニをいじめていました。
「おい、お前たち、どこに行くんだ?」サルが呼びかけてきます。
「鬼ヶ島に鬼退治に行くんだ。厳しく辛い冒険の旅。報酬は一日一個のキビ団子と成功の暁には多少の名誉が与えられる」
「何だか分からんがそのキビ団子を一つくれんかね。それだけの価値のあるものかが知りたい」
「いいだろう」桃太郎はキビ団子をサルに差し出します。
「桃太郎さま、いけません」イヌとキジが同時に叫んだ。
「サルにそれをやるぐらいなら私にください」イヌが言いました。
「いえ、私です。私にください。私が最初にあなたの家来になったのですから」キジが叫びました。
それを見ていて興味を引かれたのか、サルが木から降りてくると、桃太郎の手からキビ団子を攫い取ります。大きく開けた口の中にキビ団子を放り込むと、サルは大きく目を剥きました。
「なんという旨さ。舌が蕩けるようなとはこのことだ」
サルはうっとりとした目で感想を漏らすと、言葉を続けました。
「兄貴。キビ団子のためならどこまでもついて行きますぜ」
見事に罠にかかったなと桃太郎が内心ほくそ笑んだのは秘密です。
一行は漁港を探し回って、一隻の船を手にいれました。有り体に言うと盗んだのです。
小さな帆を上げると追い風を受けて、船は鬼ヶ島へと一直線に進みました。
船の上で一夜を明かした桃太郎が目を覚ますと、目の前にサルイヌキジが並んで桃太郎を覗き込んでいました。
「桃太郎さま。本日の分のキビ団子をください」サルが手を出した。
桃太郎がキビ団子を目の前に三個並べると、サルが素早くそれを丸ごと攫い取りました。それを口に放り込もうとしたサルの腕にイヌが噛みつき、キジがその眼を突こうとします。
「ええい! 止めろ! 他人のキビ団子を奪った奴には二度とキビ団子はやらん」
そう桃太郎が言うと三匹はたちまち大人しくなりました。自分の割り当てのキビ団子を口に含むと、遠くを見ている目でゆっくりと咀嚼します。
「ああ、なんと旨いんだ」サルが言った。
「まるで天国にいるようだ」とキジ。
イヌだけは無言でしたが、その欲望の眼は桃太郎の腰にぶら下がっているキビ団子の袋に向いています。
その後は風に恵まれ、船は矢のように進みます。やがて前方に恐ろし気な形をした島影が見えてきました。その名に負う鬼ヶ島です。
「もうすぐつくぞ。鬼ヶ島だ」桃太郎が宣言しました。
ところがサルがその言葉を遮ります。
「桃太郎さま。俺たちは船に残ります。無くすといけないのでキビ団子の袋は俺が預かっておきましょう」
桃太郎はこれに抗議します。
「何を言っている。お前たちも戦うんだ。そのためにここまで連れて来たんだぞ」
「ついて行くとは言いましたが、一緒に戦うとは言っていませんよ」サルが指摘しました。
「ええい! この後におよんで」
桃太郎は手を振り回しました。
「よし、いいか。最初に鬼の首を持って来た者にキビ団子を一つ与える。それから後は鬼の首五つにつきキビ団子を一つだ」
「それを先に言ってください」犬が叫びます。
「お先に」キジが空中に飛びあがります。
「あ、この野郎」サルが叫ぶと船の櫓に飛びつきました。
船が今までよりも速く走り始め、そして衝撃とともに鬼ヶ島の岸壁にぶつかりました。
サルとイヌは素早く飛び降りると、桃太郎を後に残して島の奥に見える砦へと向けて突進を開始しました。
やがて血まみれのキジが血まみれの鬼の首をぶら下げて戻ってきました。よく見るとキジの片足が折れています。
「桃太郎さま。ご所望の鬼の首です。キビ団子をください」
慌てた桃太郎がキビ団子を投げるとキジはそれに飛びついて貪り食いました。
ああ、とキジがため息をつきます。「足の痛みも忘れるこの旨さ」
「おい、足が折れているが大丈夫か?」
「大丈夫です。飛ぶ分には問題ありません。褒美のキビ団子を忘れないでくださいね」
キジが飛び去ると今度はサルとイヌが戻って来ました。どちらも鬼の生首を束ねて背中に背負っています。
「桃太郎さま。キビ団子をください」
驚いたことにイヌの尻尾はちぎれているし、サルの片目は潰れています。だけど二匹はそんなことは苦にもしていません。
与えられたキビ団子を恍惚の眼差しのままガツガツと食べ終えると、二匹はまた島の奥へと駆け戻ります。
桃太郎もまた刀を抜くと砦へ向かって進むことにしました。
そこへ片羽が折れたキジが地面をはいずりながらやってきました。後ろに鬼の首をいくつか引きずっています。
「桃太郎さま。キビ団子を」
キジは羽が折れているだけではなく、胸の辺りに矢が突き刺さったままです。大量の血の痕が砦へと続いています。それは鬼の血だけというわけではありませんでした。
鬼の首は四つしかありませんでしたが、その光景にビビった桃太郎はキビ団子を放りました。まともに歩くこともできないキジは地面を転がりながらもキビ団子にたどり着きます。
「ああ、旨い。旨い。もっと食いたい。もっと食いたい。いつまでも食べていたい」
そう言ってキジはこと切れました。
ほどなく桃太郎は砦に着きました。砦の門は大きく開かれ、あたり一面血だらけです。門の周囲には首を失った鬼の体がごろごろしています。
さらに奥へと進みますと、もっと激しい惨劇の光景が広がっています。やがて前方に鬼の首の山が二つ聳えている所に出ました。
そこではイヌとサルが倒れた鬼たちから首を切り取っています。今は女鬼と子鬼の首を集めているところです。
桃太郎の姿に気づくと血まみれの二匹は駆け寄って来ました。二匹とも目が血走っていて、全身の毛が血でぐっしょりと濡れています。サルの腕は折れ尻尾は千切れています。イヌは後ろ足を引きずっているだけに見えましたが、その腹部から赤いぶよぶよした何かがはみ出していることに桃太郎は気がつきました。
「桃太郎さま。キビ団子をください」言葉とともに血まみれの手が二本差し出されました。
ひいっ。小さく呟くと桃太郎はキビ団子をばら撒きました。
イヌとサルがいがみ合いながら、散らばったキビ団子に飛びつき片っ端から自分の口へと押し込みます。
食べながらも、ああ、や、うう、との声にならない呻きを上げます。
「旨い。旨い。この世にこれほど旨いものがあろうか」
「なんでもする。何でもするからもっとキビ団子を」
もはや砦に一匹の鬼もいないことを確認すると、桃太郎は砦の宝物庫から財宝を運び出し、島の港にあった船に積み込みました。
ここでサルとイヌを放置して船を出せば、一切の後顧の憂いもなくなるはず。桃太郎はそう考えていました。鬼退治が住めばキビ団子を欲しがるだけの家来はむしろ邪魔なのです。特にキビ団子の残りが少なくなった今となっては。
「後一回だけ財宝を運びこめば出航だ。お前たち、砦から運んで来てくれるか。俺はその間に船の出航の準備をする」
イヌとサルが姿を消すとすぐに桃太郎は船の帆を張り、もやい綱を解きました。櫓を握り、さあ漕ぎだそうという段になって、イヌとサルが駆け寄って来ました。
「桃太郎さま。砦にはもう財宝がありませぬ」サルが言います。
「嘘を言うな。まだ残っていたはずだぞ」桃太郎は叫びました。自分で確かめたのだからこのことに間違いはありません。
「いいえ、ありませぬ」サルとイヌは主張すると止める間もなく船に乗り込んできました。
「さあ行きましょう。桃太郎さま。ところでキジの野郎は?」
「キジならかなり前に死んだ」
「そうか。あいつ、死んだか。これでキビ団子の割り当てが増える」サルとイヌが喜びました。
船は海に出ます。だが良い風がなかなか吹かず、その歩みはのろのろしています。
退屈な日々が過ぎて行きます。毎朝イヌとサルが桃太郎を起こしにきて、両手を差し出してこういうのが日課となったのです。
「桃太郎さま。今日の分のキビ団子をくださいませ」
日を経るにつれ、イヌとサルの人相が変わっていきました。目は大きく開き、いつもぎらぎらと血走っています。その目はぎょろぎょろと常に周囲をねめつけているのが分かります。自分の腰にぶら下げているキビ団子の袋を、彼らが常に睨んでいることに気づき、桃太郎はぞっとしました。
うたた寝をしてちょっと目を覚ますと、サルとイヌがキビ団子の袋に鼻を押し付けて匂いを嗅いでいたこともありました。彼らは涎を滝のように流していました。
今の彼らの中にあるのは、地獄の飢えにも似た強烈な渇望。そう表現するしかありません。
船が陸に着きさえすれば、この二匹を撒くこともできよう。それまでの我慢だ。桃太郎は自分にそう言い聞かせて、心の裡を奥に隠したまま務めて平気な顔をしていました。
「一日に一つでは足りませぬ」ある日イヌが言いました。「もう一つください」
「ならぬ」桃太郎は断じます。
もはやキビ団子の残りは少なくなっています。ここで割り当てを増やせば、残りはあっと言う間になくなってしまうでしょう。キビ団子が完全に無くなったときに、この二匹がどうなってしまうのか。桃太郎はそれを恐れていたのです。
「私はもう長くありません」イヌが主張しました。「この通りハラワタがはみ出して腐りかけているのです。だから残りの命の分、キビ団子をたくさんください」
「桃太郎さま。もうこのイヌめは始末してしまいましょう」サルが口を挟みました。
「キビ団子をもう一つ貰えるなら、私がイヌを始末します」
「なんだと! このサル野郎」イヌが吠えました。
「ごく潰しは死ね!」サルが言い返しました。
耐えきれなくなった桃太郎は二匹のど真ん中にキビ団子を投げました。サルとイヌが同時にそれに飛び掛かり大乱闘が始まります。
だが結果はサルの勝ちでした。すでに死にかけていたイヌがサルに勝てるわけがなかったからです。
勝ち取ったキビ団子をほうばると、血まみれのサルはイヌの死体を海へと流しました。
ついに船の上は一人と一匹になってしまいました。
風が吹かない日々が続き、船旅は長引きます。ついには積んでいた食料が尽きる羽目に陥ってしまいました。もっともサルはもはやキビ団子以外は一切口にしようとはしなかったので、これで困ったのは桃太郎だけでした。
毎日毎日キビ団子は容赦なく減っていき、ついには残り一個となってしまいました。
ここまできてついに桃太郎は決心しました。最後の一個のキビ団子を布に包みなおすと、空になったキビ団子の袋に小さなガラクタを詰め込みます。
次の日の朝、サルが来て言いました。
「朝です。桃太郎さま。キビ団子をくださいませ」
「うむ。いまやるぞ。好きなだけ食べるがよい」
桃太郎はキビ団子の袋を海に向けて投げました。その一瞬、サルは恐ろしい目つきで桃太郎を睨みましたが、袋の後を追って海へと飛び込みました。
今だとばかりに桃太郎は櫓へと飛びつき、船を押し出します。その背後では沈み行くキビ団子の袋を求めてサルが下へ下へとどこまでも潜っていきます。そしてその手がようやく袋に届いたとき、猿の体から力が抜け、袋を握りしめたまま遥か海の底へと沈んでいきました。
三匹のキビ団子亡者からようやく自由になれた桃太郎ですが、危難はそれで終わったわけではありません。まだまだ岸は遥かに先なのです。そして食料は手元に残ったたった一個のキビ団子だけなのです。
船の上で飢えに苛まれた桃太郎は手の中に残ったただ一つのキビ団子を見つめていました。
それは甘くてとても良い匂いを放っています。だがこれを食べれば何が起きるのかは桃太郎にはよく分かっていました。
来る日も来る日も、桃太郎はこのキビ団子を見つめていました。
頬はこけ、体は痩せて行きます。キビ団子は相も変わらず甘い匂いを流し続け、ついに桃太郎の我慢は限界に達しました。
食べては駄目だと分かってはいましたが、桃太郎の手は勝手に動き、キビ団子を口に放り込みました。
噛んでは駄目だと分かってはいましたが、それでもキビ団子を噛みしめるのを止めることはできませんでした。
天国の味。確かにそうでした。キビの甘さの中に、魂が希求する何か素晴らしいものの味が輝きます。自分がそれまでずっと求めていて、しかもそのことに気づいていなかった味。
口腔を満たす馥郁たる天上の香り。
心の中に溶け込んで来る強烈な快感。
地獄もかくやとばかりの絡みつく衝撃。
どうして自分は今までこれを食べなかったのだろう。自分はこれを食すために生まれて来たのだ。何と人生を無駄にしたことか。
そう桃太郎は思いました。
深い満足の後に今度は凄まじい飢餓感が襲ってきました。それは今までの飢餓とは比べ物にならない強烈な飢えでした。
もっと食べたい。このキビ団子を。その思いだけが桃太郎の頭の中一杯を満たしました。
よろめく体を気力で支え、桃太郎は櫓をこぎ始めます。だが船は遅々として進みません。
この船は重すぎるのだ。そう断じると、桃太郎はせっかく積んだ金銀財宝を海に投げ込み始めました。金銀の飾りが、大判小判の山が、そして無数の煌びやかな名品が、次々と波間へと没していきます。
刀も投げ捨てました。鎧もそれに続き、手甲脚絆も同じ運命を辿りました。
少しでも船を軽くし、少しでも早く岸につくのだ。桃太郎の頭の中はそれだけで一杯でした。
その努力の甲斐あってか船は進み始め、やがて元いた浜辺が見えてきました。
浜辺についた途端、桃太郎は船を飛び降りました。船はそこに放置したまま、桃太郎は故郷へと向けてよろよろと走ります。
海岸を抜け、街道を抜け、平地を抜け、山へと踏み込みます。飢餓で衰えたその体にムチを打ち、ケモノ道へと躊躇わずに踏み込みます。懐かしい景色の中を抜け、ようやく家へとたどり着きました。
「お爺、お婆、キビ団子。キビ団子はどこだ。キビ団子をくれ!」桃太郎は叫びました。
返事はありません。きっと爺は山へ柴刈りに、婆は川へ洗濯に行っているのでしょう。
もしや作り付けのキビ団子はないかと台所を漁って、それが無いと見てとるや、桃太郎は裏の畑に回りました。
そこにはお爺が丹精込めて作った怪しいキビ畑があります。手あたり次第に千切り取ったキビの穂に桃太郎は齧りつきます。
もの凄くまずい。まずいがその中に、少しだけ、あの天国の味の息吹が感じ取れました。
両手に千切り取ったキビの穂を持って、それをひたすら食べ続けながら家へと戻ります。
これで爺婆が戻るまで何とか凌げるだろう。そう思って床に座っていると、声がしました。
「桃太郎さま。キビ団子を」
桃太郎は跳びあがりました。後ろを振り向いてみると、そこにはサル、イヌ、そしてキジがいたのです。
三匹の体はわずかに透き通っています。
「キビ団子が食べたい」折れたボロボロの羽を振りながらキジが近づいて来ます。
「キビ団子をくださりませ」折れた四股で地面を這いずりながらイヌが近づいて来ます。
「キビ団子はどこだ」びしょ濡れの姿のまま片目の潰れたサルが近づいて来ます。
「キビ団子はない。お前たち消えろ!」桃太郎は絶叫しました。
「キビ団子の匂いがする」キジが嘴を桃太郎の手に突き刺しました。
「キビ団子を隠しているだろう」イヌが桃太郎の腕に噛みつきました。
「キビ団子。俺のキビ団子」サルが桃太郎の耳に噛みつきました。
「おお、キビ団子の味がする」キジが叫びます。
「腹いっぱい食うぞ」イヌが叫びます。
「天国の味だ」サルが叫びます。
桃太郎の悲鳴と共に、いつまでもいつまでも、くちゃくちゃという咀嚼の音が家の中いっぱいに響きました。
その日の柴狩りは意外に手間取ったのです。お爺さんは重い荷物を背負いながら玄関の扉を開けると中に足を踏み入れました。
入るなり、むっと血の匂いが鼻につき、思わずお爺さんは後ずさりをしました。
土間一杯に広がった血だまりのただ中に、不思議なことに今まで見たこともない大きな桃の種が一個だけ転がっていました。
その種は全体がなぜかキビの粉と噛み痕にまみれていました。